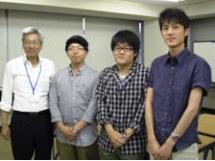| 2011年6月18日(土)に開催された「あいち交流会」の報告 | ||
2011年6月18日(土)午後、花車ビル北館の5階会議室において、愛知県技術士会会員や技術士(一次、二次)の新合格者との技術交流を目的とする「あいち交流会」を開催いたしました。会場準備や資料整備のためにご協力いただいた中部大学の学生さん3名や、飛び入り参加を含め「、参加人員は25名でした。 14:00~14:05 開会挨拶 野々部代表幹事 14:05~15:05 ベテラン技術士による発表 (発表15分、質疑応答5分) ① 環境分析の動向と資格 佐々木晃一氏 (環境) ② 建設コンサルタントでの保全業務 岡本利朗氏 (建設/総合) ③ 藻類を利用した二酸化炭素固定化技術の開発 行本正雄氏 (衛生工学) 15:20~16:40 新合格者による発表 (発表15分、質疑応答5分) ④ 自動変速機設計と私 池田 実氏 (機械) ⑤ 環境技術維新を目指す、あいち環境研究会について 石神勝博氏 (電気電子) ⑥ PCの仮想化技術とシンクライアントによる新しいオフィスの可能性 加藤欽哉氏 (情報) ⑦ 自己紹介と現状活動について 落合敏正氏 (金属) 17:00~18:00 技術交流会 3名のベテラン技術士による意見発表、および、4名の新合格者による自己PRと意見発表に基づいて、多くの質疑応答があり、活発な意見交換が行われました。 佐々木氏は、自己紹介の後、環境分析の現状を踏まえ、環境分析の信頼性向上を目指すための技術士の在り方について意見を述べられました。 岡本氏は、自己紹介の後、建設コンサルタント会社での橋梁の点検・詳細調査・補修設計業務の概略を述べた後、老朽化が進んできた社会資本ストックの安全性・信頼性を確保した長寿命化対策について提案しました。 行本氏は、陸上植物に比べて増殖速度が大きく、年間を通じて生産が可能で、オイル生産量も大きい藻類を利用したCO2削減・バイオ燃料の研究の関する最新動向の解説を行いました。 池田氏は、ご尊父様も技術士で、ご活躍されていたエピソードを話されました。自動変速機設計に当たり、苦労話とチームプレイについて話されました。 石神氏は、環境技術の維新を目指すという「あいち環境研究会」の設立の背景や目的と、現在活動中の3つの分科会の内容の説明を行いました。 加藤氏は、PCの仮想化技術がPCの管理・情報漏えいのリスク低減・省エネをもたらし、シンクライアントによりオフィスや就労状況の新しい形態の可能性を示唆されました。 落合氏は、経歴の紹介とベリリウムアルミ合金の開発に関する体験論文の内容と、専門知識を趣味のバイクの加工に活かして、自作カスタム・マフラーの開発等の活動と、今後の抱負を述べられました。 講師の皆さんと3名の学生さんも最後まで技術交流会の参加していただき、親交も深めることができました。
担当幹事 (行本正雄、竹下敏保、山口昇三) |