

  |
第三十番
清水寺

|
巡礼日 | 平成二十二年一月二十四日 |
|---|---|---|
| 山号・寺名 | 音羽山清水寺 | |
| 宗派 | 北法相宗 | |
| 所在地 | 京都市東山区清水1-294 | |
|
奈良時代、宝亀九年(778)開創の京都でも有数の古刹。音羽の滝の清水から清水寺と称されるようになった。古都京都文化財の一部として世界遺産に登録されている。
西国三十三所観音霊場第十六番 |
||
| 清水坂
お寺への参道、大勢の参拝者であふれていた。 |
仁王門
応仁の乱後の室町時代平成十五年(2003)解体修理。重要文化財。 |
| 鐘楼
慶長十二年(1607)再建。梵鐘は室町時代。鐘楼、梵鐘とも重要文化財。 |
西門(さいもん)
寛永八年(1631)再建。神社の拝殿風なのが珍しい。重要文化財。 |
| 隋求堂
享保三年(1718)再興。千鳥破風が漆喰のコテ絵になっている。 |
石仏群
隋求堂北奥に千体あまり。鎌倉時代のものも。 |
| 三重塔
寛永九年(1632)再建。昭和五十九年(1987)解体修理総丹塗りを復元。重要文化財。 |
田村堂(開山堂)
寛永十年(1633)再建。創建の坂上田村麻呂夫妻、元祖行叡居士、開山延鎮上人を祀る。重要文化財。 |
| 轟門
江戸時代初期。本堂への中門。ここで拝観料を払って本堂へ。重要文化財。 |
廻廊
轟門と本堂を結ぶ。 |
| 朝倉堂
江戸時代初期再建。創建は永正七年(1510)に越前守護大名の朝倉貞景寄進。重要文化財。 |
奥の院
寛永十年(1633)再建。本堂と同じ舞台造り。重要文化財。 |
| 地主神社(じしゅじんじゃ)
境内内にある清水寺の鎮守社。縁結びの神とかで、参拝者に若者が多かった。仁王門前の狛犬はこの神社のもの。重要文化財。 |
釈迦堂
寛永八年(1631)再建。昭和四十七年(1972)豪雨により倒壊したが旧材で復元。重要文化財。 |
| 本堂
寛永十年(1633)再建。舞台造りの絶景ポイント。国宝。 |
百体地蔵堂
釈迦堂奥に控えめに建つ。 |
| 音羽の滝
寺名の元となった{黄金水、延命水」とも呼ばれる清水が流れ落ちる。順番を待つ長蛇の列が。 |
境内図
拡大図 |
| 御朱印 | |
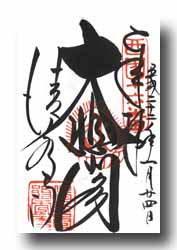 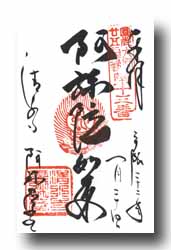 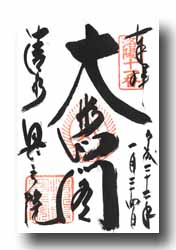 |
| あとがき |
| 京都でも有数の観光スポットとあって参拝者でいっぱい。20年ぶり4度目の訪問だが、これまでは単に観光だったので、本堂と音羽の滝ぐらいしか印象に残っておらず、鮮やかな仁王門や三重塔に目を見張った。塗装が落ちて木肌が見える古いままも味があるが、塗りなおされた鮮やかさも、これはこれでいいものだ。
(清水寺ホームページ) |
  |