

  |
第三十二番
石山寺

|
巡礼日 | 平成二十年二月一日 |
|---|---|---|
| 山号・寺名 | 石光山石山寺 | |
| 宗派 | 東寺真言宗宗総本山 | |
| 所在地 | 滋賀県大津市石山寺1-1-1 | |
| 奈良時代の天平19年(747年)、良辨僧正により開基され、平安時代の多くの文人に親しまれた寺である。特に紫式部が源氏物語の構想を練った所と伝えられていて式部ゆかりの寺として名高い。 | ||
 |
 |
| 東大門
格子窓などで近くへ寄らないとよく見えない仁王像が多いなかでここはそのようなものが無く遠くからもその威容がよくわかる。 |
くぐり岩
石山寺の名の由来になったように寺域全体が堅固な岩山となっている。手水場にあるこのくぐり岩は大理石でできており自然に体内くぐり状態をなしていた。 |
 |
 |
| 毘沙門堂
安永2年(1773年)の建立。 |
御影堂
お堂の中には開祖良辨の他に、石山寺ゆかりの空海、淳祐(菅原道真の孫)の遺影が納められている。 |
 |
 |
| 本堂(国宝)
懸架木造建築最古のもの、内陣は平安中期、外陣は修補のもの。本堂脇に源氏の間がある。 |
硅灰岩(けいかいがん)
立て札によると石灰岩が花崗岩と接触した際の熱で変質したもので新鮮なものは純白だという。大きな褶曲が大自然の力を感じさせる。国の天然記念物。 |
 |
 |
| 源氏の間
紫式部が7日間ここにこもって源氏物語の構想を練ったといわれる。 |
源氏物語図屏風(複製)
八曲一双(江戸時代)。蓮如堂に展示。源氏物語五十四帖を丁寧に描いてあり、物語を読んだことはない私でも見飽きることがなかった。 |
 |
 |
| 芭蕉の句碑
源氏の間を読む。 「あけぼのはまだむらさきにほととぎす」 |
鐘楼
源頼朝の寄進と伝えられている。袴腰の漆喰が美しい。 |
 |
 |
| 経蔵
かっては国宝の淳祐内供筆聖教を収蔵していた。滋賀県では珍しい校倉造り。手前に見える岩はそこに座ると安産になると伝えられている腰掛石。 |
めかくし石
めかくししてこの石を完全に抱けば諸願成就という言い伝えがある。 |
 |
 |
| 梅園
3箇所ある梅園のうちの第2梅園。今は花の季節には少し早かったですが、紅梅のつぼみが色づいてました。 |
ロウバイ
紅梅には早かったがロウバイがよい香りを放っていました。 |
 |
 |
| 月見亭
石山寺で一番見晴らしが良い場所に建っている。かって歴代の天皇もここからの眺めを楽しまれたという。 |
瀬田川の眺め
月見亭は立ち入り禁止になっているのですぐそばから。紫式部もみたであろう瀬田川の眺めは「石山の秋月」として近江八景のひとつになっている。 |
 |
 |
| 多宝塔(国宝)
源頼朝の建立といわれ多宝塔は石山寺のシンボルである。この形式では日本最古のもの。 |
無憂園
本堂下を奥にはいったところにあり、種々の花が咲く園内です、今はたくさんの実をつけたピラカンサが目を惹きました。 |
| 御朱印 | |
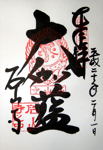 |
| あとがき |
| 硅灰岩の岩山だったこの地は昔は今よりももっと名勝だったに違いない。京の都から近いこの地を数多くの平安の女人が参篭したのもうなづけます。花の寺としても有名なのでこの次は花の季節に訪れたい。 |
  |