| World > Africa > Democratic Republic of the Congo | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Artist | ||||||||||||||||
|
FRANCO & LE T.P.O.K.JAZZ |
||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
|
1980/1981 |
||||||||||||||||
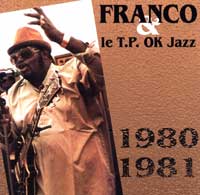 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Review |
||||||||||||||||
| 1980年、フランコはヨーロッパへ拠点を移したのを期に、VISA1980、EDIPOP、PASSEPORTの3つのレーベルを起ち上げると、堰を切ったかのような怒濤のアルバム・リリースをおこなう。 本盤は、EDIPOPレーベルから81年にリリースされた"LE QUART DE SIECLE DE FRANCO DE MI AMOR ET LE T.P.O.K. JAZZ" シリーズ全4集のうち、第2集から第4集までに収録されていた楽曲を中心とする全5曲構成。この時期のアルバムはいずれも劣らぬ高水準で、本盤が抜きん出てすぐれているわけではないが、フランコを語るうえで無視できない重要曲'TAILLEUR' が収められている。 'TAILLEUR' とは“洋服の仕立屋”の意味だが、別名'MOKOLO TONGA ABOTOLI TONGA NAYE' (「針の持ち主が針に刺さる」)というように、じつは78年にフランコが逮捕されたときの司法長官だったケンゴ・ワ・ドンドへの当てこすりとのうわさが絶えないいわくつきの作品である。フランコはその旺盛な批評精神と執念深さでもって、これまでも名指しこそしないものの、あきらかに特定の人物への個人攻撃と思われる曲をいくつも書いてきた。モブツ大統領のお気に入りで「模範的なザイール国民」となったのをいいことにやりたい放題していたから、かれのことを内心快く思っていない人物も少なからずいた。 フランコの逮捕劇は人びとのそんな怨念が一気に噴出したかたちで起こったものだったといえるかもしれない。しかし、それでも懲りることなく復讐に出たフランコという男の執念深さはハンパではない!こんな人間とは絶対にお近づきにはなりたくない。そこで、時計を逆戻りさせてフランコ逮捕にいたるまでのいきさつについてくわしく論じてみることにしたい。 77年に“ジャト”Diau Antoine 'Diatho' Lukoko (Lukoki) 、翌年に“ジョー”Djo Mpoyi Kaninda のふたりのリード・シンガー、そしてアフリカ版ブエナ・ビスタの中心人物としていまふたたび脚光を浴びているギタリスト“パパ・ノエル”をメンバーにむかえたTPOKジャズは、78年、初のヨーロッパ・ツアーを敢行した。 コンサートはブリュッセルとパリで計4回おこなわれた。宣伝不足もあって成功というにはほど遠かったが、ピンク・レディや松田聖子のケースに似て(笑)、ヨーロッパを制覇した国際派スターの凱旋帰国のはずだった。だが、かれらを待っていたのはマスコミによるフランコ叩きの一斉砲火であった。 フランコはヨーロッパ・ツアーへ出る前に、'JACKY' 、'HELENE' 、'SOUS-ALIMENTATION SEXUELLES' を含む4曲からなるカセットを発売していた。カセット発売のかたちをとったのは当局の検閲をかいくぐるねらいがあったと思われる。しかし、カセットとはいえ、そのあまりに過激な歌詞内容にキンシャサっ子たちは色めき立ち、耐えかねたマスコミは一斉にフランコを弾劾した。 なかでも'JACKY' と'HELENE' の2曲がやり玉にあげられた。'JACKY' はオーラル・セックス、アナル・セックスからスカトロにまで及ぶ変態趣味のかぎりを尽くした内容だったという。 司法長官のケンゴ・ワ・ドンドは、フランコの帰国を待ってただちに召喚した。わいせつ罪にはあたらないと抗弁するフランコにたいし、当局はその判断をフランコの母親に委ねることとした。日頃から母親思いのフランコだけに「それだけは勘弁してほしい」と必死に嘆願したが、かれの願いは聞き入れられず母親のマキエッサが呼び出された。カセットを聴かされた老母はショックを受けて大いに嘆いたことはいうまでもない。 こうして78年9月末、フランコとTPOKジャズのメンバーは逮捕された。そして、むこう2ヶ月間のレコーディング禁止と、同じ期間、“アン・ドゥ・トゥロア”とEDITIONS POPULAIRES の閉鎖が命ぜられた。また、カセットを所有する者にも48時間以内にそれを当局へ提出することが厳命された。 10月はじめ、出廷したフランコにたいし裁判所は罰金2500ザイールと懲役6ヶ月、メンバーには懲役2〜4ヶ月というのきびしい判決を下した。主要メンバーのうち、ダリエンスト、ンドンベ、エンポンポの3人は無罪とされたが、シマロ、シェケン、パパ・ノエルら10人は演奏に深くかかわっていたとして、フランコの必死の庇い立ても甲斐なく有罪となった。高級官僚待遇で「模範的なザイール国民」に贈られる特権であった'the National Order of the Leopard' も剥奪された。 フランコは収監後まもなく、ひどい神経衰弱にかかり入院するはめになった。そして逮捕から3週間を過ぎたころ、フランコとメンバーたちは釈放された。なんでもモブツ大統領の特別な計らいによるものらしい。フランコはモブツの寛容に心から感謝したにちがいない。しかし、冷静に考えてみれば、今回の逮捕から恩赦にいたる一連の流れはあらかじめモブツ大統領の指示のもとで仕組まれたものではなかったか。モブツは手のかかるわがままな友人にお灸をすえようとしたが、フランコの恨みが自分にむけられないよう細工したのだと思う。その甲斐あって、'TAILLEUR' で報復攻撃されたのは直接指揮にあたったケンゴ・ワ・ドンドだった。 釈放後、フランコはザイールの音楽家連盟UMUZAの会長職を辞任する。また、ザイール唯一のレコード・プレス工場であったMAZADISの株式の大半を手放し、フランコの御用音楽雑誌"Ye!" も売れ行き不振により廃刊になって、ザイール音楽業界におけるフランコの独裁体制に翳りが見えはじめた。 ところで、まぼろしとなった'JACKY' と'HELENE' だが、シンプルなリフをバックに、ときどき印象的なコーラスのリフレインをはさみながらフランコの長ったらしい話が延々とつづくという、このころからフランコが得意としだした例の“説教パターン”だという。演奏時間はいずれも15分前後。注目すべきは、'JACKY' でのフランコのソロ・ギターのモチーフは、87年に発表された晩年の代表作'ATTENTION NS SIDA' 「エイズにご用心」で使いまわされているということだ。 しかしわからないのは、なんでフランコが危険な橋を渡ってまでこんな歌を発表したのかということである。おそらく「オレはなにをしても許される」という慢心があったにちがいない。フランコには、68年に検閲委員会で問題とされた'LA BERITE DE FRANCO' (FRANCO ET L'OK JAZZ 1967/1968 (AFRICAN/SONODISC CD 36518) 収録)がそうだったように自分の密事(みそかごと)を歌にしたがるミョーな性癖があった。と同時に、センセーショナルな話題をふりまいて、つねに世間の注目を浴びていたいという人気稼業ならではの習性が働いたのだろう。 この事件以降もフランコは'TAILLEUR' のように相変わらず諷刺の歌を歌いつづけたけれども、インモラルな歌を発表することはついになかった。 逮捕の翌年、ザイール国内でのほとぼりを冷ます意味から、ガボン、カメルーン、ベニン、コート・ジヴォアール、トーゴ、セネガルと西アフリカ諸国をまわる大規模なツアーを決行した。そのあと、ふたたびヨーロッパでもコンサートをおこなった。 そして、翌80年、フランコはついに拠点をヨーロッパへ移してしまう。これは、心機一転の意味もあったろうが、より現実的には録音機材や技術が数段すぐれていること、さらにマーケットを拡大させるうえではヨーロッパにいたほうが都合がよかったことが理由として考えられる。また、子どもたちに高等教育をほどこしたいとの家庭的な事情もあったらしい。かくしてフランコは、ビジネスの中心はブリュッセルに、生活の中心はパリにとそれぞれ拠点を構えた。 さて、ここでようやくヨーロッパ移住後につくられた本盤の中味についてふれる段となった。 最大の注目曲'TAILLEUR' は、ミディアム・テンポのいつものフランコ節だが心なしか歌もビートも沈んだ調子で重ったるい。同じくフランコ作の'ILUSSE' も負けず劣らずヘヴィで初心者には少しとっつきづらいかもしれない。とはいえ、不惑をこえて策を弄すことなく剛球一本で勝負するフランコの存在感には圧倒されるものがある。 これらにくらべるとジョーが書いた'KATEBE' はまだ青い。コーラスの妙に酔っているフシがある。また、後半のセベンでのザイコっぽいアニマシオンやバタバタしたドラムスはTPOKジャズにふさわしいとは思えない。背後でオフ気味に聞こえるストリングスらしき音の正体はサックスだろうか? シマロの'MAMBA' は、粘着質なメロディ・ラインといい、スローからアップ・テンポへの急展開といい、いかにもかれならではの感じがするし、それを易々と演奏してしまう技術の高さには目をみはるものの、あまりに予定調和で目新しさが感じられないのが難点か。 それよりも元トゥ・ザイナのジェジェが書いた'AMROZI YA PAMBU' がいい。うねるようなホーン・セクション、ズシリと迫ってくるドラムスとコンガが旋回するギターを煽りに煽り、セベンの迫力では本盤随一といえよう。 みてきたとおり、本盤は全体に重たい印象があって、花といえそうな要素があまり見あたらない。しかし、黒光りする重厚感がコアなフランコ・ファンには、それはそれで魅力に感ぜられることだろう。 |
||||||||||||||||
|
(11.25.03) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
前の画面に戻る |
||||||||||||||||