2015年8月30日(日)の午後に開催した第2回例会「講演会」は、ウィルあいち(愛知県女性総合センター)の1階セミナールーム1・2で、作家の鳴海風先生(元㈱デンソー勤務、博士(経営情報科学))にお話をいただきました。鳴海先生には2013年4月に開催した定時総会の特別講演として、「江戸の天才数学者-世界を驚かせた和算家たち」の講演をいただきましたので、2回目の登壇でした。
1.本講演会のテーマは【日本の古人から視る日本の技術史】
技術開発において避けて通れない事は“王道=過去の積み上げの延長線上からの脱却”です。しかしながら王道から外れる事は限りなく失敗に近づく事と同義語です。しかし、技術職である我々は困難であっても日々変わり続ける事に挑戦をし続けなければなりません。失敗の低減と成功率の向上、それらを両立し実現するためには、先ずは王道の背景や王道から離れることが困難であった理由を事細かく知る必要があります。それらを知るのに最適な学問が歴史です。歴史には過去の多くの偉人たちの思いや願いが込められた結果の学問です。特に我々により近い影響のある技術史に関しては、より深く熟知しておく必要があると考えて、この講演会を企画しました。
2.内容
13:30~13:35 開会挨拶 (愛知県技術士会 代表幹事 野々部顕治)
13:35~15:45 鳴海先生による講演 「星に惹かれた男たち - 江戸の天文学者 間重富と伊能忠敬」
15:45~16:00 質疑応答
16:00~16:10 閉会挨拶 (日本技術士会中部本部愛知県支部 支部長 水野朝夫)
16:30~18:00 技術交流会
3.講演の概要
現在の日本技術の立ち位置や、ノーベル賞に受賞状況おさらい、国際ランキングの説明、日本の課題を述べられ、貿易収支の内訳、貿易収支は単純に額面でだけなく、技術貿易収支も勘案すべきという話題提供をいただいた後に本題。天文学・暦の重要性や探求の歴史的背景と、江戸時代に建造された天文台や簡天儀の紹介。
高橋至時と間重富は、改暦御用のために出府下命。その同じ年に伊能忠敬(当時51歳)が高橋至時(当時32歳)に出会い入門をするという、必然とも言える程の奇跡的な出会いがありました。寛政の改暦を実現して太陰暦からの脱却を果たした高橋至時は、更なる暦の精度向上の目指し、偶々手に入れる事ができた“Astronomia of Sterrekunde”を“ラランデ暦書管見”として纏め上げました。この知識を応用した測量を行い、当時としては、かなり正確な日本地図を描き始めたのが伊能忠敬でした。高橋至時の死後、翻訳作業を続けた間重富と高橋景保は、“新巧暦書”を完成させ、これが後の天保暦の土台となりました。これらの歴史背景と登場人物、彼らの行動から視る天文学への熱い思いを細かく解説いただきました。
講演後の質疑応答では、「天地明察」がフィクションであることがあまり知られていない話が上がり、会場を盛り上げていただきました。
 |
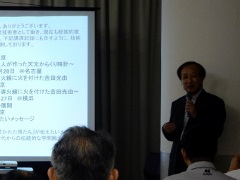 |
 |
講演終了後、16時30分から1時間半ほど、同会場地下の食堂にて、鳴海先生を交えての技術交流会を開きました。鳴海先生にもご参加いただき、後援に関する詳しい内容や歴史的な裏話などで花を咲かせていただきました。
 |
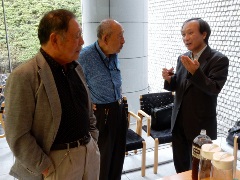 |
担当幹事
竹下敏保、盛田直樹、山口正隆
共催
日本技術士会中部本部愛知県支部