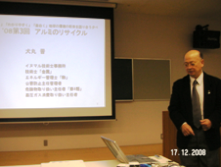| 2008年12月17日(水)に開催された「2008年度後期第3回 なごや環境大学愛知県技術士会講座」の報告 | ||
以下の通り、なごや環境大学の愛知県技術士会講座"「楽しく」「わかりやすく」「面白く」地球環境の将来を語り合う夕べ"の第3回目が開催されました。 ・日時 : 2008年12月17日(水) 18:30〜20:00 ・場所 : なごやボランティア・NPOセンター 12階集会室 ・講師 : 犬丸 晋 (技術士(金属部門)) ・題目 : 「アルミのリサイクル」 アルミニウム(以下、アルミという)は、われわれの日常生活で広く使われている。たとえば、アルミ箔はクッキングホイルとして、乳酸飲料の蓋、薬のパック、さらには、ビールなどの飲料缶に多く使われている。これらのアルミ製品は、一度、使うとゴミとして廃棄されている。講師はアルミ延会社に約40年間勤務した経験と知識をもとに、電気の缶詰といわれるくらい多量の電気を消費して得られたアルミについて基礎てきな知識を持ってもらうために、①アルミの地金を得るために、なぜ多量の電力を消費するのか? ②アルミ缶の製造工程は高度の技術を要し、③アルミ缶や箔がなぜわれわれの生活に多く使われるのか? ④アルミ缶や箔のリサイクルの現状 について説明した。アルミのリサイクル(溶かして地金として回収)のエネルギーは地金精錬の5%以下であり、鉄などに比べリサイクルしやすい金属である。 アルミ缶が一般家庭に定着したのは、利便性を追及したわれわれの生活様式によるもので、すなわち、'one way' と呼ばれている。たとえば、かつては、ビールや酒は酒屋さんから過程に配達してもらい、空き瓶は酒屋に回収してもらっていたが、最近では、ビールを飲んだ後、缶はゴミとして捨てられている。飲料缶に年間約40万トンのアルミ材が使われている。これらの地金はすべて海外から輸入している。電力消費量にすると60億kwhいう多量の電力である(一般家庭で1戸あたり年間400kwh使うとすると、150万戸分に相当する)。アルミを効率よく使うにはどうしたらよいかを考えることは、省エネルギー、言い換えればCO2削減に貢献できることになる。われわれ家庭で消費するアルミは5〜100μと薄いものであり、再溶解ロスは大きくリサイクルできないものもある。アルミの長所である軽くて、強く、錆びないという特性を生かして、自動車、鉄道、建材などに長期間使えば、より大きいメリットが得られる。すなわち、より多くのCO2削減が達成できる。そのためには、われわれの生活様式、「利便性の追及に走りすぎていないか」を変える必要があるのではないか。これこそが、講師の提案である。
これからも、毎月第3曜日になごや環境大学愛知県技術士会の講座を続けます。次回(第4回)は2009年1月21日(水)の18時30分からです。技術士(電気電子部門)の杉本利夫氏による講演「省エネ対策活動の今昔」です。より多くの皆様のご参加をお待ちしております。 (文責 犬丸晋) |