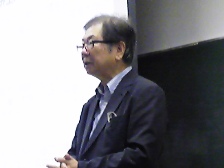| 2011年6月15(水)に開催された「2011年度前期第3回 なごや環境大学愛知県技術士会講座」の報告 | ||
以下の通り、なごや環境大学の愛知県技術士会講座"「楽しく」「わかりやすく」「面白く」地球環境の将来を語り合う夕べ"の2011年度前期第3回目が開催されました。 ・日時 : 2011年6月15日(水) 18:30〜20:00 ・場所 : なごやボランティア・NPOセンター 12階集会室 ・講師 : 長谷川正 (技術士(化学部門)) ・題目 : プラスチック材料のリサイクル利用の実態。日本と中国との比較 この講座では、資源の少ない日本ではプラスチックの原料である原油を全量海外から輸入されてる現状で、如何にその貴重な資源を有効に利用するかを考えるためのヒントを提供するものです。 私が主張したかった点は次の5点です。 1)日本が1年間に消費するプラスチック量は約1,000万tだが,、その中で再度リサイクルされて再利用されている量は21%で、残りはガス化や発電が50%、埋立や単純燃焼24%であり、原料再利用比率が大変少ない。 2)地球資源の循環的社会を構成するためには、3R(Reduce,Recycle.Reuse)の徹底が重要である。そのためには国民全体の環境に対する意識を高める必要がある。 3)リサイクル材料で再利用された製品は。身近のベンチ,学習用品、合成木材、家電リサイクル法品、自動車再利用部品、事務用機器などに使われているが、市民としても、この運動を促進協力が必要である、 4)地球環境保持の目標であるCO2放出減量対策、省エネルギー化対策として、プラスチックのリサイクル効果を再認識したい。CO2減少効果を比較すると、リサイクル使用パレット2,800kg.、ガス化や発電利用1,600kg、単純燃焼900kg、高効率発電610kgである。自動車工業会でもリサイクル材料の採用を促進し、プラスチックPP材1.4kgCO2発生量がリサイクル材料では0.1kg、スチール材2.0kgCO2発生量がリサイクル材料では0.5kgへ減少している。プラスチックのリサイクル材料の使用で、CO2の発生量を10分の1に減少できる。 5)化石原油を原料にするプラスチックを循環型社会の形成のためには、自然植物原料であるとうもろこし、サトウキビ、じゃがいもなどを原料にして乳酸を分離し、重合したポリ乳酸を主原料にした生分解性ポリマーが注目されている。アメリカDow社が先行しているが、最近では中国、タイ国でも国産化が進み、すでに数10万tのスケールに発展している。これまでは価格が発展の阻害になっていたが、中国,対、ブラジル、タイなどで競争力成功している
次回(2011年度前期第4回)は、2011年7月20日(水)の18時30分からです。技術士(機械部門)の杉本漢三氏による講演「本当のエコカーとは何でしょうか」です。皆様ぜひご参加いただきますようお願い申し上げます。 (文責 長谷川正) |