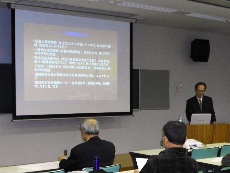| 2011年11月16日(水)に開催された「2011年度後期第2回 なごや環境大学愛知県技術士会講座」の報告 | ||
以下の通り、なごや環境大学の愛知県技術士会講座"「楽しく」「わかりやすく」「面白く」地球環境の将来を語り合う夕べ"の2011年度後期第2回目が開催されました。 ・日時 : 2011年11月16日(水) 18:30〜20:00 ・場所 : なごやボランティア・NPOセンター 12階集会室 ・講師 : 斉藤保彦 (技術士(環境部門)) ・題目 : 環境に関する調査の今昔、そして近未来 ●受講者 20名 (アンケート回答数) ●内容 私の携わってきた「環境調査」について、大学時代の調査事例、社会人時代の環境アセスメント、環境監視(モニタリング)業務体験などを、環境調査の歴史も踏まえながら紹介し、近未来の環境に関する調査の課題、方向性についても言及しました。 1.「環境調査」とは 広義の環境調査、狭義の環境調査について説明し、環境調査の歴史を測定分析機器等の歴史とも絡めて説明しました。 2.誰でもやってる「環境調査」のあれこれ 意識するしないに関わらず、幼少時代から誰でもやっている環境調査(身近な人の観察、植物・昆虫採集など)について説明しました。 3.私の携わってきた環境調査について 大学時代に行った調査、研究室で行われていた調査事例を紹介しました。また、社会人(環境コンサルタント)として実施した原点としての環境調査事例、その後の業務実績(環境アセスメント、環境監視等)、トピックとなる調査事例を紹介しました。 4.環境調査のキーワード キーワードとして、5W1H、五感(+第六感)、地域密着、環境影響波及、コミュニケーションなどを挙げ、強調すべき内容を説明しました。 5.今後の環境調査の動向 今後の調査技術の進化、高度化の展望について説明するとともに、得られた結果を判断するのはあくまで人間というスタンスを踏まえ、風評被害の防止と絡めて、結果を伝える技術、コミュニケーションの重要さを強調しました。
●まとめ、感想 ・「楽しく」「わかりやすく」「面白く」話ができたかどうかは疑問ですが、「わかりやすく」には心掛けてお話しさせていただきました。受講者の皆さまのアンケートの内容を踏まえて、自己評価、反省し、次の機会に生かしたいと考えています。 ・震災、放射線、水質浄化、河口堰の問題、環境アセス制度、環境調査請負業務の考え方、関連用語の使い方など、幅広く、多くの方にご質問いただきました。明確な回答ができない面もありましたが、今後の業務に生かしていきたいと考えています。 ・今回、こうした発表の機会を与えていただき、ありがとうございました。 これからも、毎月第3水曜日になごや環境大学愛知県技術士会の講座を続けます。次回(2011年後期第3回)は、2011年12月21日(水)の18時30分からです。技術士(金属部門)の下村勇一氏による講演「私たちが原子力エネルギーを安全に享受できるための代価」です。皆様ぜひご参加いただきますようお願い申し上げます。 (文責 斉藤保彦) |