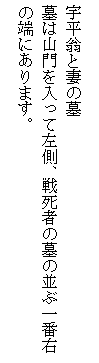明治のはじめに、この下市場村のあたりで、官有林の無断伐採の事件があり多くの人々が取調べを受けました。
そのとき、宇平という一人の村人が自首して一身に罪をかぶったそうです。そして拷問だか、刑罰だか分かりませんが、百叩きといわれる鞭打ちの仕置きを受け、明治七年八月十一日に牢死してしまったそうです。
この官有林伐採の材木で、旧慈眼寺の伽藍を作ったという話が残っており、そんなに古い話でもないことを考えると信憑性は高いようです。おそらく公のものである山林を伐採して、公の施設である寺院を建てることに、村人たちは何の抵抗もなかったでありましょう。時期的にも、旧本堂の棟札に嘉永七年(1854年)の年号があることから辻褄も合わないことはありません。それでも事件から十数年たって、新政府が捜査を始めたというより、幕府の詮議を新政府が引継いだと考えるほうが自然かもしれません。あるいは、明治維新政府によってなされた廃仏毀釈運動によって事後的に犯罪として扱われたのかもしれません。事実このような弾圧で取壊された寺もいくつかありました。
この過酷な取調べの中、村人たちは宇平という一人の男に因果を含め自首を頼んだということです。いわゆる人柱に立てたということでありましょう。このような村のために誰かを犠牲にするという人柱説話はそれこそ日本中の村に残っているようです。個人意識の強い現代では考えられないことでしょうが、当時の稲作集落はそれくらい運命共同体であったのでしょう。考えてみれば、たった一人でそんな大量の木材を運べるはずもないのですが、この宇平を罪人とすることにより、詮議は終わったようです。
この宇平さんには、盲目の娘が一人あって、若い頃にあったことがあるという話を親から聞かされたという方は何人もおられるようです。そんな人達がいまだに宇平さんとその妻のお墓に花を手向けてくれています。墓には「孤嶽儀峯信士」と「忍興操貞信女」と夫妻の戒名が刻まれています (平成15年4月13日)。
* 「慈眼寺整備だより」第6号に載った伊藤忍氏の原稿を参考にさせてもらいました。