山と旅のつれづれ 暮らしのエッセー(3)  PC絵画 いまどきの旅行ガイドブック
 岩国 錦帯橋 若かりし頃、旅行などそう度々行けるような生活環境ではなかったが、旅好きの私は旅行ガイドブ ックなどをよく読んだものです。
そのころのガイドブックは一人の旅行作家とか随筆家とか云った肩書きを持つ職業人が個人の視 線で旅先の印象や話題や見所、 交通手段など文章主体でエッセイ風に仕立て上げた内容が主で、 おいそれと旅に出る機会や余裕のない私にも読めばそれだけでも 気分的には旅をしているような満 たされた気分に浸ったものなのです。 そうした事前情報をもとに、たまに旅に出た時、そこが初めて足を踏み入れる場所であっても、何 となく懐かしさのような感覚に浸るこ
とさえ珍しくなかったと思っている。そして、それが旅の面白さ の大事な要素だと思っている。 何の前知識もなく巡り歩くと見落としてしまうし、見落としたことさえ気がつかずに通り過ぎて、ただ その地を巡ってきた記憶だけで満
たされた気持ちになっているような気がする。 団体よりも個人旅行が好きな私は乗り換え電車がどのホームから発車するのか分からず、もたも たしていて無駄な?時間をつぶし
たり、ドライブ中、道に迷ったりなど珍しくないが、振りかえって見 ればそんな経験がその旅の印象を一層深いものにしていて後々まで 記憶に留めていることに気が つく。 たまには機会が巡ってくる団体旅行や小グループの旅でのあなた任せの気楽さもそれはそれで 楽しいものだが、前者と後者は同じ
旅でも別物だと思っている。だから私は個人の旅の機会を多く 持ちたいと考えている。 そういう理由で海外旅行に行く自信がない。だいいち外国語がまったくできないのでは外国で個人 旅行など無事にできるはずがない
し、団体旅行でガイドさんの旗ばっかり気にしながらカルガモの子 供みたいにしがみついてぞろぞろと動き回ることなど想像しただけで ぞっとする。 いまどき珍しくもない海外旅行の経験者の話を聞くとそんなことはないと云うが一種のバリアに包ま れた状態での行動には違いがな
いだろう。 もともと、頭の中身がうすくて勉強する気が起こらず語学など習得する気にもならなかったにもかか わらず、 そんな過去を棚に上げて、いまさら不勉強を反省している。 さて、本題のガイドブックだが、自分も一緒に旅をしているような気持ちにさせる三四十年前の旅 のプロによる随筆風の出版物は今
やほとんど葬られてしまって、当世風の紋切り型というか、マニュ アル型と言うか単なる説明型になってしまって文学的な香りがまったく 影を潜めてしまっている。・・と 思う。 どのガイドブックにも目立つのが、「行く、観る、食べる、遊ぶ、買う、泊まる」或いは「足、観光、味、 プレイ、土産、宿泊」などの項目
別に何人かのスタッフによって構成されていて、写真ばかりで読み 物というより見るものになってしまっている。 マニュアル的で調べやすいことは確かだが、大事なものを忘れて来ているように思えてならない。デジタル時代の自然な成り行きなの かもしれないが、このことを嘆くのは何時の間にか年寄りになっ てしまったかもしれない自分の僻みだろうか。 一部に個性的なゆったり旅を紹介した熟年世代を意識したと思われるガイドブックも散見されるが サイズが大きくそれに恐ろしく値段
が高い。旅の友としてポケットやバックにしのばせて歩けるような 気楽さに程遠いことが惜しまれる。 いま振り返れば生き方の転機 「誤診−妻の災難−」から、早いもので既に三年。 同人誌「小さな足跡」掲載を機に加筆再構成のうえ、 あえて重複部分も含めて記録します。 その日「2002年12月8日」かみさんは朝からわきの下のあたりに痛みを感じ食欲がないと言う。珍しいこともあるもの だと思いながら
も、日曜日のこととて大して気にもせず、翌日、日ごろからかかりつけの医院で筋肉痛とストレスと診断 を受け、筋肉注射と痛いときに 飲むと言う薬を処方してもらってきた。 ストレスで病気になるような環境にはいないはずだが、筋肉痛については粘土こねを趣味で日常的にやっているので、 さもありなんと 納得してしまった。 このことが重大な事態を招くサインだったとは知るはずもなかった。 治るどころか悪くなる一方で、三日連続で医院に通ったが三日目の深夜、激痛と呼吸困難に陥り未明に救急車を呼ぶ はめになって
しまった。診断の結果は総胆管結石の発作と重度の肺炎の併発。結果的に総胆管結石の発作を四日間 も放置してしまったことによる 極端な体力の低下が肺に感染症を引き起こしたということらしい。とにもかくにも、病院に 収容された安堵感か鎮痛剤が効いているの か、ICU「集中治療室」で妻はようやく穏やかな表情を見せたものの、首の 動脈につながれた点滴と酸素吸入でその痛々しさに私は言 葉を失ってしまった。 救急担当医の「総胆管結石と重症の肺炎です、血液の組成が変わって出血した場合血がとまらなくなる恐れがあり 危険な状態です、
念のためケイタイ電話を手放さないで下さい」と落着いた口調で告げられ、私の視線は意味もなく宙 を泳いでいた。気持ちが動転し、身 体が地球の引力を感じなくなってしまったような錯覚にとらわれていた。 よく言う頭の中が真っ白になる、というのはこういうことなのだろう。
未明に救急車に導かれるとき、救急隊員が妻の人差し指の先にケーブルの付いた洗濯物挟みのようなものを付け、 しばらくスイッチ を入れた計器板を凝視したあと私に「緊急入院の可能性があります。帰りの足のことを考え、車で別行 動で病院へ急いでください」とい われ、まさか、と思いながらも一抹の不安にかられながら、支度をし、冷え冷えとした真 冬の深夜の病院救急窓口の扉を押した。しば らくの間待たされたあと、別室に通され救急医師との前述の対話に、そ の重大性を思い知らされ、愕然としてしまった。 あの、「洗濯ばさみ」は血液中の酸素量を調べるもので、それを調べれば肺の機能が極端に低下していることが一目 瞭然であり、血
液の組成に影響することは救急車の段階で診断できることが理解できた。 それから10日間ほど、一応快方に向かっていると思われたものの、その日妻は腰の痛みを訴え張り薬を処方された。 張り薬について は妻も私もかぶれる体質なので注意していたが果たして予想通り発疹ができてしまった。ところが、こ れを担当医は肺炎治療薬の薬害 と判断したようで(実際そうかも知れないが)抗生剤の種類を変更した。これが肺炎に は全く効かず悪化することになってしまったよう だ。 このことは、病状が快方に向かいだしたとき、居合わせた医師から聞いたことだが、肺炎治療の抗生剤は種類が幾 つかあり、肺を満
たしている菌に対してまったく効かない場合があるということだった。全身が衰弱し、排尿が出来ず一 日一キロを上回る体重が増加し、 むくみで水ぶくれ状態になってしまった。この異常を妻は担当医に必死で訴えたのだ が届かなかったようだ。 この現象を、女は幾つになっても女で美容的な観点から気にしていて、異常を訴えはしたものの、異常なむくみという よりも、太ったと いう認識があり、気持ちの隅にぬかりがあったとしか思えないのだ。 急激な衰弱を伴いながらも体重が10キロも増え、それを維持するために心臓はフル稼働を強いられていたに違いな いのだ。
食べたいというので、用意して持って行ったフルーツを持つ手が小刻みに震え、口の周りが同じように痙攣していて、 ようやく一口食 べたものの、それ以上の食欲が起こらず、喘ぐようなしぐさに、何となく薄ら寒さを感じながらも、よもや、 このことが緊急事態に至るサ インだったなど、思いもよらないことだった。 12月28日朝、負担に耐えかねた妻の心臓の鼓動が止まった。
急性心不全。苦痛に耐えられず、必死でナースセンターに辿りついたあと、動けなくなり車椅子に乗せられたあとは 何も憶えていない という。気がついた時はICU「集中治療室」で人工呼吸器のパイプを気管の入り口まで通され、機械 の力で喘いでいた。 急を聞いて駆けつけ途方に暮れていた私に若い救急医はこう告げた。「ご主人ですか。今朝、心臓が止まりました、 今は人工呼吸器
で動いていますがこのまま数日続くか、それまでに急変があるかも知れません、心の準備をしておい て下さい」―可能性も無いと言う 事ですか?「・・・・・・・・・ちょっと」。突き上げる激情を押し殺して泣き崩れる私の耳に、 医師の靴音が冷酷極まりない響きを残して遠ざ かった。 度重なる不運の中に身を委ねる妻に、心底哀れを思った。そして、重大な事態になすすべのない自分を呪った。
傷心に打ちひしがれつつ持ち帰った洗濯物を整理していて、妻のパジャマの上下が、ずたずたに切り裂かれている のを目の当たり にして、心肺蘇生の際の医師や看護師のうろたえぶりというか、緊迫した空気が伝わってきた。 このことは後に看護師からいきさつを聞かされ、衣類を切り裂いたことに対する謝罪をされるまでもなく理解してい た。 無意識状態のとき、妻は私の母や本人の実父(共に故人)それにその前の代の知らない人々にまで会っていたと言 う。そして母より
先に死ぬわけには行かないので、どうしてもシャバに戻らなければならないなどと【懇談】をしていたと いう。潜在意識はこの世とあの世 の間のバリアを取り払っていたようだ。 世間では、無意味な延命装置と思われがちな人工呼吸器の助けを借りて、翌日、幸いにも意識を取り戻した妻は衰 弱と気管内挿管
人口呼吸器で言葉も出せない状態ながら、かろうじて動く手指で糸くずのような文字で筆談が出来るよ うになってきた。その内容は自 分がこのまま死ぬかも知れないという意識をもにじませていた。 しかし、その精神力は悲嘆に打ちひしがれた私の気持ちの中には、かすかな明かりを点じた。
妻が意識を取り戻したとき、呼吸器の他、七本のマカロニパイプにつながれ、間断なく薬の注入や排泄で身動きも出 来ず、また、当 然その体力もなく、横たわっているだけなのに、全身の極端な疲労を訴えていた。仮死状態のときは意 識がなかった訳だから、苦痛を 感じることもあり得ない。そうして、意識がうっすらと回復してきたとき、苦痛や極端な疲 労感の中で、ようやく『死』を意識したということ なのだろう。 妻が自分の意思で「死ぬかもしれない」と意識したとき、その、苦痛の訴えを受けて私は生への踊り場へ辿りついたと 歓喜したのだ。
いま、振り返ってみると、不思議な取り合わせに感慨をあらたにしている。幸い、一日半の仮死状態の 中で脳は損傷を受けていなかっ たのだ。悪くすれば脳が死んで植物人間になってしまう可能性もあったかもしれない中 で、それは次第に明るさを増して来た、そして歓 喜に変わった。 ICU集中治療室で10日間、人工呼吸器も外され2003年1月17日現在、おそらく驚異的とも云えそうな快復力で今は 退院の日を待
ちわびている。 もう一つの病名、「総胆管結石」については、肺炎の快復後の検査で異常がないことを確認し安堵している。 ただ、不思議なことに総胆管に接するかたちで臓器の外側に結石が確認されている。医師はこれには首をかしげる ばかりだ。まるで アコヤ貝が真珠を抱いているみたいだ。しかし、異常がなければ気にすることでもなさそうだ。 生身の身体の危うさもろさを余りにも身近な存在を通して、強烈なインパクトで実感させられた闘病生活だった。
入院から35日目、本人はもとより看病の立場で身も凍るような日々がようやく過去になりつつある(2003年一月現 在)。意識が戻って しばらくの後、自力で眼を開けた時、そこに映ったのは、デジカメの液晶画面に納まった、生まれた ばかりでまだ名前も決まっていない 初孫の画像だった。12月31日に生を受けた私たちの初孫は、まかり間違ってバア サンの生まれ変わりなどと、のちのち、言われないで 済んだことを安堵している。 緊急入院から五十日、順調に快復してめでたく退院の運びとなった。
この、悲痛な体験からほぼ三年。あらためて、但し、めでたく検証してみる。 妻は、二十年ほど前に肝機能にいくらかの病変があることを自治体が呼びかけている簡易人間ドックの結果分かっ ていて、ウイルス
性は否定されたものの、原因不明ということで、経過観察ということになっていた。ただ、漢方薬「ショ ウサイコトウ」を服用してみます か、と言う医師の助言にしたがって習慣的に服用を続けていた。そんな折、同薬の服用 で年間三、四人が副作用による肺炎で死亡し ているという新聞記事に接して、動揺したが、薬はどんな薬でも程度の差 はあれ副作用を伴うといわれているし、恐れることでもなかろ うと、軽く考えていた。 そのときは、幾人かの不幸な人々を頂点として死には至らなかったものの、公表されない中軽度の或いは重度の副 作用現象がピラ
ミッド型に広がりを作っていたかもしれないことなど、思いもよらなかった。 今回、妻の危急と、この副作用との関係について、私は素人判断に過ぎないが濃厚であっただろうと確信するに至っ ている。 肺炎という病気は風邪をこじらせるとか、その他の病気によって、体力、免疫力が落ちたときに併発するのが一般的 であるはずだ
が、妻は肝機能のほんの一部にわずかな病変があるとはいえ至って元気で、風邪をひいた訳でもないの に、ほとんど突発的に「重度 の肺炎」と診断された。しかも、仮死状態に陥りながらも、快復に向かったら、信じられない ほど早く健康を取り戻してしまった。 この病気は私自身が十数年前に経験しているのでその経験からみて、表面的には元気を取り戻しても予後は非常に 長く、定期的な
レントゲン検査や薬との付き合いは当分の間続くことになる。まして、60 歳代ともなれば、なおさらだ。 それが、病後の定期検査では早期に肺のくもりは、ひとかけらを残してなくなっているので目出度く「無罪放免」となっ てしまった。薬の 副作用は薬をやめれば収まるといわれているが、その、典型を見るおもいだ。 ひとかけらの痕跡は、いわゆる病歴の証人のようなもので、心配はいらないという。
さて、ここでこの一連の事故或いは事件かもしれないいきさつについて、医師や私自身の対応について、うらみつら みと、反省につい て述べてみたい。 第一に日ごろから、かかりつけの開業医が懇意なだけに、基礎的基本的な診療態度を忘れていたのではないかと言 う事があげられ る。明らかに誤診であり、このことは、その後に起こった事情が事情だけに、うらみつらみが募る。 次に、救急車を呼ぶ時、以前に歯医者から貰っていて使っていなかった鎮痛剤を応急的に服用して少しは苦痛がや わらいだ状態
で、妻が「朝まで何とかなるから大げさな救急車など呼ばないで」と言うのを無視して、ためらいながらも 119をプッシュしたこと。収容さ れた病院で「朝まで遠慮していたら危なかった」と云われて、安堵したこと。 12月28日の朝、妻が意識を失う直前に自力でナースセンターまで辿りつき、もうろうとしながらも助けを請う行動ができ たこと。このこ
とは、おそらく生死を分ける決定的な瞬間であったと確信している。 これがなければ朝の回診のとき冷たい骸になり果てていたことだろう。 不運と幸運が入り交じって、それでも現在があること。収容された病院でも危機を招き危機を乗り越えたことなど、病 院の医師や看護
師を恨むべきか、感謝するべきか、いまだに解らない。また、病院と云えども年末年始の手薄な体制 になっていたことも不運を増幅さ せたとおもっている。 二人の息子が母の病状を慮って、病院不審から転院を主張するので、パイプだらけで動かすことなど無理ないしは 不可能であろうこ
とを承知で12月31日の夜、家庭では大晦日の団欒に満ちているはずのその時刻に、近くて全国的 にも評価の高い病院の冷たく静ま り返った夜間受付に父子三人で相談に行ったこと。転院については病状の把握や担当医師の了解を得る こと、休日体制で物理的にも 無理なことなど、説明を受けて息子を納得させたことなど、よかったか良くなかったかはと もかく、他に方法などなかったことなど、思い 起こしてみて、結果がよかったのだから、これでよかったのだろうと今にな ってはたぶん、楽しく思い起こしている。 そんな心境の中で、この度の危急が不運と幸運が交互にバランスをとりつつ、最後に幸運の比重が僅かに勝った、 綱渡りのような結
果に、今はまぎれもない幸運を実感している。一時は諦めて悲嘆に暮れていたとき、かつて眼にした 琵琶湖畔のシルバーマンションが 私の頭の中を占領していた。 原住地で周囲から哀れみのまなこを注がれつつ、惨めな独り暮らしを強いられるくらいなら家屋敷を売り払って、その 資金を終身利 用権にあてれば、琵琶湖の風景を眺めつつ過去から脱却して新たな隣人関係も生まれることだろうと本 気で考えていた。 あの日、2002年12月31日、デジタルカメラの液晶画面におさまっていた、その日に生まれた直後の初孫はすでに 三歳、可愛いさ
かりを迎えている。 六十二歳で伴侶の死の瀬戸際にさらされて、悲嘆にくれた、いまわしい経験にかんがみて、いまから六十三年前、私 が三歳になる直
前、医師の誤診の結果三十六歳の若さで四児を遺して死に追いやられた私の実父の、無念の心境 と、母の悲嘆はいかばかりであっ たかと、生前多くを語らず祈りの生活に徹しつつ八十三歳で天寿を全うした母の気持 ちを今さらながらに思いやっている。 それと同時に、今回の妻の危急が、父の「誤診による死」の不幸な再現につながらなかった幸せを今しみじみとかみ しめている。拾っ た命だ、たのしくやろう。 いまがよければ 事実かどうかは、よく分からないが、一般的におもわれているような学生時代の開放的なくらしが私にはなかった。
経済社会のしがらみから解放されて、自由な時間を得たとき、若かりし頃のくらしの再現をめざして着々と実行している 健全なシニア は多い。 私のシニア人生はそういった夢の実現ではなく、気がつけば失われていた、かけがえのない時間を手遅れにならない 内に取り戻すこ とにあった。 定年自由人の多くは、十代後半から二十歳前後の若かりし頃の「振り返れば限りなく楽しかった青春時代」があった はずだ。 私は、そうした、経験すべき大事な一ページをどこかに置き去りにしてきたことにさえ気が付かずに、丁稚小僧という 前近代的な「修
業」という名のもとに身を置いてきた。 15歳という年齢は、そんなことさえ後々になってからでないと分からないほどに、自分自身の将来 像について考える 時、幼く未熟な思考でしかなかった。 こういうふうに書き出すと、不遇な境遇を強いられた不幸な人生の経験者と受け取られるかも知れない。父親の記憶 をまったく知らな
い私はそのことだけでも、その通りなのかも知れないが、同時に勉強がまったく苦手で大嫌いであった ことも紛れもない事実で、そのこ とが思考の未熟さを助長していたのかもしれない。 私にとって15の春はあれほど嫌いだった「勉強と学校」から開放される、まことに楽しい節目だったのです。すくなと も、その時点では
本気でそう考えていた。だからいまでも反省はしても後悔はしていない。その代わり、結果的に失わ れていた若さと自由の楽しさを「職 業からの大多数の人々よりも早い卒業」に照準を合わせて、取り戻すべき時間の実 現を夢に見てきた。 さて、それでは未熟な思考の結果として関わってきた職業が苦痛や不遇をかこってきたのかと云えばそうでもない。 なべ底不況のさなかに卒業 戦後復興が一段落して、その後に起こる繊維業を中心としたいわゆる「ガチャ万景気」との狭間でなべ底不況といわ れた不運な時機
に卒業したものの、いくらかでも納得できる就職先など身の置きどころさえなく、緊急避難的に片隅の 小さな就職先にとりあえずの救い を求め、気がついたら数の上では珍しい業種に就いていて、希少業種であるがゆえ の面白さの中にいたようなものだ。このことは、努 力もしないで結果的に幸運な選択だったかもしれない。 独立開業後は下請けでもなく元請けでもなく、他人や上司にへつらうこともなく、人を使わず、使われもせず、成功も なく、さりとて大き
な失敗もなく、高度に発達した資本主義社会の複雑で責任の重い歯車に組み込まれもせず、それで いて、孤軍奮闘という単純ながら 適度な刺激があってか、独立後37年もの間、飽きても離れられない不思議な魅力を ほとんど無意識的に感じていた。 いま、振り返ってみれば極めて個性的で稀有な道を歩いてきたと思う。
結果をまとめれば丁稚小僧も未熟な思考も、深く考えもせず身の置き所さえあれば当面の食いっぱぐれはなかろう と、飛び込んだ職 場が半世紀近くに及ぶ多分いい意味での腐れ縁?のはじまりだった。 そうした意識が微妙に変ってきたのは、二人の息子を社会に送り出して、身軽になってからだった。家計を支えると いう欠くべから
ざる目的が希薄になったとき、時として猛烈に忙しい家業を、誰のために働き、金を稼ぐのかという基本 的な意味が曖昧になり、社会 に対して役に立っているともおもえないこの種の労働という行為の生活の中に占める位 置に疑問をもちはじめた。 いまからなら、それまで、漠然と意識してきた遠い少年の時代に何処かに置き忘れてきたことに気がついた、「若さと 自由な時間」を
ひょっとしたらこれからでも具体的に取り戻せるかもしれないと思うと、気持ちが躍ったのです。 そういう意識の変化の中にいながら、一方で47年に渡って関わってきた仕事の、心の中に占める重みも無視できず、 方針が決まって いながらも、自分で決断に至らず、一年一年と引き延ばし、とりあえず仕事を継続することで当面の気 持ちの迷いの解決を先送りする という、姑息な手段で自分と自分の妥協に甘んじてきたその優柔不断な日常に、ある 種、恵まれていると思いつつ嫌悪していた。 自分の意思で現役からの卒業 そんなとき、「神のご託宣」にしては、少々どころか極端に手荒い後押し(第二十二話、誤診-妻の災難-)に遭遇して、 ようやく決断力
を得た。 世間一般の就職年齢よりは数年早く、また、兄弟たちより七年ないしそれ以上早く実社会の小さな歯車の一隅に組 み込まれた私 は、そのぶん早く仕事から離れて自由の身になることが信念だったはずなのに、気がついてみれば、63 歳になっていた。それでも取り 返しのつかないほどの「失ったもの」はなかった。それで良かったのだろうと思う。 考えてみれば25歳までの10年間を除けば、ひとり或いは夫婦で、「製造直売わが道を行く」を貫いてしまった、それで いて、世間並み
に世渡りをやってきて、苦心も苦労もあったとは云え、複雑で神経をすり減らす人間関係の中に身を投 じてきたはずの多くの勤労者と 比較すれば、取引関係はともかく、日常的に上下関係を知らず、妥協もせず、何時の間 にか身についた職人気質を一途に通して、対 人的には多分にウブなまま、生活が成り立ってしまったという、終わって みれば幸せな現役人生だったのではないかとしみじみと思う。 そんなことをあれこれ振り返っているうちに、月日の経つのは早いもので66歳になってしまった。仕事を卒業して早く も三年。新たな人
的つながりも多分積極的に求めてきたし、思いがけない趣味も見出した。 だいたい、私に、ものを書く或いは描く楽しさ(苦しさでもあるが)を発見するなど、夢想だにしなかったのに、広い意味 で自分史とでも
言えるのではないかと思えるような書きものを自分では信じられないほど書き残してきている。しかも、 一念発起して何が何でも書き記 すなどと構えたわけではない。気がついたらそういうことになっていたのだ。こんなこと は、仕事を卒業して限りなく自由な時間を得たこ とによる最大の成果だと思っている。 じぶんを変えたパソコンとの出会い。 ふとしたことから、息子がゴミにするというパソコンをどうせゴミにするのなら、パソコンのことは何にも知らない親父の 所へ捨ててくれ
れば親父である私が心おきなく、正真証明のゴミにしてやると。なにせ、百円の投資もしていない気楽さ でホントに壊れるまで使いまくっ たが、今やパソコンは生活の一部として必需品になっている。書き残すという、形に残 る楽しさに導かれたきっかけは、何と捨てられる 運命にあったパソコンのワープロ機能に出会ったことによる。人生、何 処に転機が待ち受けているか分かりません。犬も歩けば・・・で す。 勤め人ではなかったので、制度上の卒業(定年)ではなく、自らに言い渡す卒業の、その後に起きうるであろう予期し 得る、或いは予
期しえない展開や、新たな日常生活環境に対する期待は同時に不安も内在していて、複雑な思いがな かった訳ではないが、いまで は、大いに自由な時間を謳歌していると確信している。 先々のことを考えれば、この国の年金財政のお粗末さは無視できることではないが、そこまで考えるとこの先短い人 生が更に短くな
りそうなので、考えないことにしている。 それに、私たち夫婦の場合は制度上の公的年金は老齢基礎年金だけ。不足分については、任意加入の公的年金そ の他でカバーし てきている。強制的、責任的な制度だけに頼らず、限りなく自助努力による積み重ねの結果の上に生 活している。自己責任が原則の 自営業者なので当然のことだが、せめて、これくらいの我儘はこの年代には許されても 良いのではないかと思っている。 考えてみれば現在の年金者生活の基礎も、この腐れ縁の結実の上に支えられている。
歩いてきた道を振り返るとき、長かったようでも、やはり短かったと思うし、その物指しで残された人生を展望すると、 ほんの僅かしか 残っていないのだ。 貪欲に自分流のくらしの楽しさを追及して、これでよかったといえるような内容の濃いしめくくりを実現したいと思う。 老 老 介 護  関東で暮らす92歳の義母は要介護認定4という。
気丈な義母は息子や娘たちとの同居を拒み、或いは遠慮してか、気楽な独り暮らしで余生を送っていた。その義母が脳梗塞で倒れて いたのは三年ほど前のことだ。一人暮らしの気楽さは、とりかえしのつかない禍根を残した。 次第に歩行困難、右腕麻痺と高齢が相まって、残りの命を懸命に支えている。 現在は老人保健施設に入所しているが、幸い、娘たちが周辺の町に住んでいるので、入れ替わり立ち代り介護や話し相手など、世話 をしてくれている。 そんな中で、ひとり遠く離れた私のかみさんは日常的な協力がままならず、5人の兄弟姉妹に頼りきっている。できることと云えば、ほと
んど定期的に二三ヶ月おきに一週間程度の出張介護というか、話し相手になってあげることぐらいだ。そんな日常の中で、何年ぶりか に夫婦で見舞いに行く機会を得た。 「老人保健施設の雰囲気に接すると気が滅入るよ」という、あらかじめ、かみさんの言に、およそ覚悟はしていたものの、本当に気が滅 入ってしまった。 施設自体は、車椅子で動き回ることのできる広い廊下やバリアフリーの行き届いた伸びやかな室内で明るい雰囲気だが、其処に収容
されている人生の大半を終えて静かに暮らす人たちの何と孤独なことか、ほとんど会話がないのだ。 コミュニケーションが成立すれば生き続けることの意味も見出せるとおもうのに、そんな元気もないのかもしれない。 ひとつのフロアに十数人の物言わぬ車椅子のグループがつけっぱなしのテレビを観るでもなく、無視するわけでもなく、うつろな眼がお おぜいの中のそれぞれの孤独を、たぶん、ほとんど「孤独」という意識もなく訴えているのだ。 そんな日常のなかで、嫌な過去や精神的苦痛を忘れてしまうような、見方によっては「幸せな認知症」にもなれず、正常な思考を保って
いる義母の「生き続けなければならないことの嘆き」の訴えに返す言葉が浮かばない。 人の命は地球よりも重い・・とは誰が言った言葉か知らないが、ウスッペラなきれいごとなど、安っぽく並べて欲しくないとおもった。 人が人として進歩し続けて以来、連綿と受け継がれてきた生命の循環。繰り返されてきたその終わり方に、この国の社会や政治はい ったい何を先人から学んできたのか、大きな疑問を感じる。 その一方で、軍事力が国際外交政策のうえで物を言うという野蛮な現実は、「生き続けるために余分な殺生をしない動物たち」より愚
かな大量破壊兵器の開発に世界が血眼になっている。 人が生を全うするための努力や工夫ではなく、より多くの生命をより残酷な手段でもって殺戮するために、巨額の資金を投入し続けて いる。こんな馬鹿馬鹿しく、空しい努力の陰で、身の自由を失った老人たちが今日もうつろな眼で義務的な最低限の介護のもとに時が 過ぎ行くのを待っている。 行政は人生の終わりを迎える人たちをやさしく処遇するのではなく、私にはどうしても「やがて消え行くゴミ処理」としか思えない。それ
に、重労働を強いられる介護職員の人件費などの待遇のひどさも行政は何を考えているのか眼に余るものがあるといっても過言では ないだろう。こうした職場は行政手動による手厚い保護と待遇の必要を感じる。 そして、そのことは、現場で働く人たちよりも、予算を削りつづける、或いは必要な増額を拒み続ける行政の在り方に革命的な変革が 無い限り解決はないように思えてならない。 かく云う私も68歳。年老いたという実感は未だないものの、すでに老境にさしかかっていると言っても大げさではない年齢になってしまっ
ている。 それに、2008年4月から施行される後期高齢者医療制度といわれる、支出を抑えることだけが目的と思われてもしようがない更なる医 療改悪に照準を合わせるかのように年齢を重ねていくわが身の行く末に暗澹たるものを感じる。 それにしても、独り暮らしの高齢者の身の危うさ、あのとき、発見が早ければ如何に高齢であってもまた違った余生が得られたであろう にと、返す返すも悔やまれるこの頃である。 葬儀について考える。(ある懇談会での話題から)  この、重いテーマに暗いイメージを重ねていたが面白いといった方がいいかも知れない展開に意外な思いがする。
もっとも、重くて暗く、しかも避けては通れない話題であればなおさら深刻さを払拭するのが人間たる所以だと思うので、考えてみれば納 得です。 この企画に対して報告というより、私見を交えた枝葉を広げて思うままに書いてみます。90歳で、要介護状態の母の介護に奮闘して
いる妻を含めた姉妹たちを、私の場合、傍目で見ながらではあるものの、老老介護の現実に直面している者として、未だ自分自身の問 題として意識する余裕がないというのが偽らざるところなのです。つまり、70歳に手が届きそうな年齢なのに、自分のことより実母、私に とっては義母の終末に如何に関わるかと言う問題で頭の中はいっぱいなのです。 そういう環境の中で気がついたことなのだが、自分自身の葬儀やその周辺の処し方については、開けっぴろげでモノが云えるのだ
が、誰が見ても終りが近いと実感できる親の葬儀の在り方については、如何に子にあたる兄弟姉妹とは言え、軽々しい言動は慎む・・ というのが暗黙の了解事項になっているような気がする。 老いた病身の親に、「どんな葬式をやってほしいか」などと聞けるはずがないし、ましてや、お婿さんの私は、事態に対して同情と沈
黙、それに、可能な協力以外になす術がないのです。 そして、そのときはゆっくりと、でありながら、突然訪れることになるのだろと・・・そして、その日を受け入れる心の準備も時間的な余裕 も充分にありながら、たぶん、どたばたして葬儀屋の思う壷にはまってしまって、思わぬ出費などの事後処理で兄弟姉妹の間で気まず い軋みが生じなければいいがと危惧している。 90歳という年齢は、向こう三軒両隣、井戸端会議に花が咲いた、見方によっては良き時代の意識を脳裏に色濃く残していると思う。当
然、ご本人は葬式のあり方もその延長線上にあるのでしょう。ところが、時代はとっくに変って地域のお寺を介在したしめやかなご近所 葬から、葬儀屋の営利業に変貌している。 それどころか、そういう時代も既に市民の間で反省の機運が生まれてきていて、考えてみれば目まぐるしく変化してきている。 自宅で送り出していた葬式の時代から、十数年前、私の母の葬儀のときはお寺の本堂でのしめやかな、しかし、半世紀に渡る年月を
未亡人で通した実母の生前を偲ぶのにうってつけの、一種明るささえも伴った通夜と大げさにはならない真宗大谷派の仏前での告別 式の費用の安さに驚いた記憶がある。そのあと、登場した民営葬儀屋によるぼろ儲けの我が世の春は、長い歴史の中では瞬間風速 的な現象を示して、飽きられてきていると私は思っている。 現に、東京では,30パーセントがご近所葬でもなく、葬儀業者の思いのままに操られた派手葬でもなく、費用を極端に抑えた地味葬が
定着しているという。 この傾向は少子化、家族や兄弟たちの生活範囲の広域化、それに、何と言っても長寿化という事情が後押しをして、今後も続くものと 思う。 そういう最近の事情を考慮すれば、私たち高齢者(自分では高齢などとは思っていないけれど、昨日、かみさんの指摘で頭のてっぺん を鏡に映して、その明るさを、嫌というほど確認して、ああ、やっぱり・・と認めるはめになってしまった)は元気なうちに、葬儀の仕方につ いて、真面目に、但し楽しく愉快に語り合い、しっかりとかたちに残しておくことが息子や娘たちへの孝行ではないかと、しみじみと思う。 無宗教葬儀というテーマであったけれど、葬儀には、仏教にしろ、その他の信仰にしろ、程度の差はあれ、やはり、関わってくると思
う。で、それは、信仰というより長年にわたって培われてきたこの国の文化としての存在だと私は理解している。信仰心がなくても、心の よりどころは必要だと思うのです。 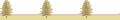 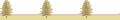 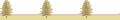 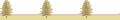 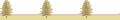 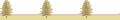 |
