| World > Africa > Ghana | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Artist | ||||||||||||||||
|
E. T. MENSAH & THE TEMPOS |
||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
|
ALL FOR YOU [REMASTERED] |
||||||||||||||||
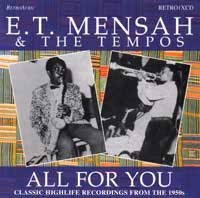 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Review |
||||||||||||||||
| 50、60年代、ガーナ、ナイジェリアを中心に西アフリカのポピュラー音楽シーンを席巻したダンスバンド・ハイライフ。1920年代、ガーナの中心都市アクラにあった黒人エリートむけの高級ナイトクラブで、パームワイン、ゴンベイ、アシッコ・ソングといったストリート・ミュージックがオーケストラ用に洗練されたアレンジで演奏されるようになった。なにせ、高級クラブだから金持ちじゃないと入れない。だから、金のない連中が優雅な装いでやって来るカップルたちを見物するために、クラブのまわりにぞろぞろ集まってきた。そこで演奏される音楽は、いつしか、かれらから“ハイライフ”と呼ばれるようになった。 E. T. メンサーは、1919年、アクラで生まれた。ブラスバンドから発展したティーチャー・ランプティ率いるアクラ・オーケストラでフルートを学んだのち、兄イェブアとアクラ・リズミック・オーケストラを結成。39年にはダンスバンド・コンテストで優勝する。 第2次世界大戦がはじまると、ガーナにイギリスとアメリカの軍隊が駐留するようになった。かれらはジャズとスウィングをもたらした。駐留兵むけにオープンしたナイトクラブではスウィング・バンドがセットされたが、軍隊から募集したミュージシャンだけではバンドを組むことができなかったので、楽譜が読める地元のミュージシャンたちが引き抜かれた。メンサーもそのひとりで、40年にサージェント・レパードというスコットランド人サックス奏者が結成したブラック・アンド・ホワイト・スポッツというバンドに加入する。そこで、ジャズのテクニックについて多くを学んだ。 大戦後は、ブラック・アンド・ホワイト・スポッツと同じ40年に、ガーナ人ピアニスト、アドルフ・ドクと、英国人エンジニア、アーサー・ハリマンによって結成されたテンポスに移籍。メンバーだったヨーロッパ人たちが帰郷してしまったためである。 いまやメンバーがすべてアフリカ人となったこのバンドで、メンサーはバンド・リーダーとしてサックスとトランペットを担当した。テンポスは、ビッグ・バンドを小規模にしたような7人編成で、テナー・サックスにジョー・ケリー、ドラムスにガイ・ウォーレン(コフィ・ガナーバ)の名があった。 50年代はじめからテンポスは西アフリカ各地をツアーしてまわった。かれらが生み出したダンスバンド・スタイルのハイライフはたちまち都市部の音楽シーンを席巻する。 本盤は、86年に、英国のレーベル、レトロアフリークが復刻した50年代のデッカ録音15曲に、新たに3曲を追加してリマスタリングした決定盤。音質が格段によくなったおかげで、テンポスの綴れ織りのように優雅で洗練された演奏がよりリアルに聴きとれるようになった。タイトル曲をはじめハイライフが14曲、カリプソとあるのが4曲、めずらしいところでサンバが2曲収められている。 テンポスのサウンドは、ジャズ・タッチといっても、黒人系の激しいタイプではなく、上品でスウィートなスウィング調。ホーン・セクションは繊細だがタフさも併せ持っていて、たんなる甘ったるいダンス音楽に終わっていない。ピアノは入っていないが、そのぶん、50年代後半ごろの録音からエレキ・ギターが前面に出てきている。同じハイライフでも、パームワイン直系のギターバンド・ハイライフのスタイルとは系統がことなり、ジャズ・ギターの奏法に近い。 このことはヴォーカルについてもあてはまる。ベチャッとしていて声を張り上げるた感じアフリカ的なギターバンド・ハイライフにたいし、こちらはダンディで都会的なクルーナー系。そりゃそうだ。ホテルやらダンスホールで、あんな具合に声を張り上げられたんじゃ、優雅にとりすましてダンスなんか踊っちゃいられないよな。 テンポスの音楽のインターナショナル(といってもアフリカにおいてであるが)な性格をあらわしているのが、歌われる言語の多様さである。本盤だけでも、英語、ファンティ語、トゥイ語、ガ語、もう1枚のアルバム"DAY BY DAY"まで含めると、さらにエウェ語、ピジン語、スペイン語の歌まである。また、アフリカのポピュラー音楽にはめずらしく、インスト・ナンバーが6曲含まれているのもインターナショナルな方向性を意識してのことかもしれない。 ガーナへは19世紀後半以降、西インド諸島の軍隊が配備されていたことからカリプソの前身であるカイソやジャマイカのメントといった音楽が入ってきていたはずだが、ここで演奏されるカリプソやサンバは、むしろ大戦後のロンドンの音楽シーンを反映したものとみるべきである。 当時、トリニダードやジャマイカはまだ英国領で、ロード・キチナー、ロード・ビギナーなど、多くのカリプソニアンたちがロンドンに来ていた。メンバーだったガイ・ウォーレンは、一時、バンドを離れてロンドンへ渡り、そこでラテン系音楽のバンドに加入する。その経験から、ジャズ・タッチのテンポスに、アフロ・キューバンやカリプソをレパートリーにとりいれることを提案した。ボンゴやマラカスを加えたのもかれの進言による。 ところが、ガイ本人はハイライフよりもジャズに傾倒していたため、50年にはバンドを脱退。リベリアでラジオのディスク・ジョッキーを数年間したのち、渡米する。ビリー・ホリデイ、デューク・エリントン、カウント・ベイシー、レスター・ヤング、チャーリー・パーカーといったあこがれのジャズの巨人たちとも出会えたガイではあったが、育った文化のちがいからアメリカ流のジャズを演奏できない自分に限界を感じてしまう。 そこでかれがとり組んだのは、ジャズのエッセンスをとりいれたアフリカ系の音楽であった。70年代前後にアート・アンサンブル・オブ・シカゴやアーチー・シェップなどのアフロ・アメリカンを中心に、アフロ・ルーツ志向の音楽が盛り上がりをみせるが、奇しくもガイ・ウォーレンはその先駆者となったわけである。ガイのレコーディングは、先ごろ、レトロアフリークから"THE DIVINE DRUMMER"(RETROAFRIC RETRO16CD(UK))としてCD復刻されている。 ところで、50年代はじめから半ばまでのロンドンのカリプソ・シーンを紹介したコンピレーション"LONDON IS THE PLACE FOR ME"(HONEST JONES HJRCD2(UK))には、ガーナの独立にエールを贈るロード・キチナーの'BIRTH OF GHANA' という曲が収められていて、ロンドンを媒介として西アフリカとカリブの距離が意外と近かったことを思わせて興味ぶかい。だからかどうか、テンポスの“カリプソ”は、カリプソそのものというより、ソフトに仕立て直されたカリプソ風味のハイライフといったおもむきである。このことは“サンバ”についても同様。 それにしても不思議なのは、テンポスの音楽がひと握りのエリートだけでなく、西アフリカ周辺の都市部でなぜ、こうもメジャーにはなりえたかということである。コンゴにグラン・カレが登場してルンバ・コンゴレーズが生まれるか生まれないかの時期(フランコのデビューはもっと遅く56年)に、早くもこんなにモダンな音楽が聴かれていたなんて、にわかには信じられない。 そこで思い出したのが、われらがディック・ミネのこと。わたしの世代の記憶では、くぐもった声をした千人斬りの絶倫ジイサン程度のイメージしかなかったが、昭和9年(1934)に発売された「ダイナ」をはじめて耳にしたとき、そのあまりにモダンでハイセンスな歌いっぷりにぶっとんだ。これが東海林太郎の「赤城の子守唄」と同年に発売され、ともにヒットしたのだ。 こういうことがいえないだろうか。当時の日本人の感受性のうち、モダニズムの面を代表したのが「ダイナ」であり、保守的な面を代表したのが「赤城の子守唄」であって、いずれかいっぽうではなかったと。 そう考えると、「テンポスがなぜ受けたかわからない」としたわたしの印象は、「赤城の子守唄」だけをみて戦前の流行歌のイメージを決定してしまうのに似て、当時のアフリカの人たちが持っていたモダニズムの側面を欠いた先入観から来るものだというのがわかってくる。 さらに、そこには「ポピュラー音楽は時代を降るにしたがってモダナイズされてくる」とする進化論的な発想が内在している。この考えでいけば、昭和30年前後に演歌が誕生することはありえなくなってしまう。そうでなくても、演歌はポピュラー音楽が退化したものだということになってしまう。演歌は、いったんインターナショナルな方向へむかったポピュラー音楽が反転した土着化現象ということはできても、けっして退化とはいえない。 誤解がないようにしたいのは、テンポスの音楽がいくらモダンだからといって、アフリカらしさが感じられないとわけではないということだ。 たとえば、コンゴでもヒットしたという'NKEBO BAAYA' などにあらわれる「カッカッカッ」という裏打ち3拍のスティックはガーナの伝統音楽の要素を色濃く反映したものだし、トゥイ語と英語を交えて歌われる'DON'T MIND YOUR WIFE' なんてカリプソっぽいハイライフの曲も、よく聴くとパーカッションのリズムの刻みかたがむちゃくちゃ細かくて複雑である。 レトロアフリークからはもう1枚、メンサーとテンポス名義で"DAY BY DAY"(RETROAFRIC RETRO3CD(UK))というアルバムが出ている。50年代はじめから60年代なかばまでの録音から選曲されているが、中心となるのは50年代後半から60年代で、ちょうどガーナが独立した時期(1957年)と重なる。そのせいだろう。演奏力が上がり洗練度が増したいっぽうで、アフリカ色はいっそうつよくなっている。伝統と現代の融合という面では、こちらのアルバムほうがすぐれていると思う。反対に、完成型に至る前の不安定さから来るスリルを求めるなら、本盤をおすすめしたい。 メンサーのテンポスは70年代に事実上活動を停止するまで、ガーナ、ナイジェリアを中心に数えきれないほど、多くの追随者を生んだ。テンポス出身者からは、さきのガイ・ウォーレン、ジョー・ケリーのほかにも、トミー・グリップマン(tb)、サカ・アクワイエ(vo)、スパイク・アニャンコア(as)、グレン・コフィ(tb)、ガーナ最初の女性歌手ジュリアナ・オキーネ(vo)、ズィール・オニイナ(tp)、ベビーフェイス・ポール・オサマデ(ts)といったミュージシャンを輩出した。このように、E. T. メンサーがアフリカ・ポピュラー音楽の成立にはたした貢献度は絶大だった。そのわりには知名度がいまひとつなのがつくづく残念に思う。メンサーの音楽を聴けば、アフリカのポピュラー音楽にたいする認識は180度変わるだろう。 |
||||||||||||||||
|
(6.25.03) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
前の画面に戻る |
||||||||||||||||