| World > Latin America > Caribe > Martinique | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Artist | ||||||||||||||||
|
MALAVOI |
||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
|
MALAVOI |
||||||||||||||||
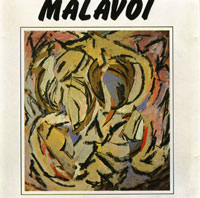 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Review |
||||||||||||||||
| 07年4月、北中正和さん監修によるワールド・ミュージック・ファン待望のガイドブック『世界は音楽でできている』全2冊(音楽出版社)が刊行された。ワールド・ミュージック系のアルバムは、ロックやジャズの名盤とちがって、評価が安定してはいないし、すぐに廃盤になってしまうことも多い。そのため、この本のアルバム選には、刊行時点での流行や市場の流通状況がかなり反映されている。これらがその音楽スタイル、あるいはミュージシャンの最良作と必ずしもいえないことぐらい北中さんは百もご承知だろうが、そうせざるを得なかったところに出版媒体の限界があると知った。 だから、せめてこのホームページではアルバムが入手可能かどうかはいっさい考慮せず純粋に内容のみを問うのがよいと思ったのである。 このことを踏まえて90年前後のワールド・ミュージック・ブームの申し子だったマラヴォワをとり上げてみる。 カリブ海小アンティル諸島に浮かぶフランス海外県マルチニーク島(人口約32万人)のアマチュア楽団マラヴォワが当時、日本でどれだけ勢いがあったかは、89年だけでCD4枚(『ジュ・ウヴェ』、『スーシュ』、『ベスト第一集』、『ベスト第二集』)、ビデオ(LD)1本("EN CONCERT")が国内発売されていたことから想像がつくだろう。しかも、これらのうち、ベスト盤を除く発売元はメジャーのCBSソニーなのだ。 同年10月には来日公演がおこなわれ、『ミュージック・マガジン』12月号では楽団のヴァイオリン担当で長老格のマノ・セゼール Mano Cesaire と文化人類学者の山口昌男との対談が企画された。マラヴォワの音楽と山口の関心テーマ、そして当時の日本社会(ついでにこの企画自体)に共通するキーワードはずばり「祝祭性」である。出身が西欧以外のミュージシャンのレコードが続々入荷し、かれらの来日公演が数多く実現するなどという事態はバブル以前には考えられないことだった。わたし自身、なんか急に世界が近く感じられるようになって、東京にいながらインターナショナルな気分に浸りつつ心が浮き足立っていたように思う。 ところが、91年のバブル崩壊からしばらくしてワールド・ミュージック・ブームも泡のように消えてしまった。銀座4丁目の山野楽器でベストセラーになり、銀座の画廊勤務、「hanako族」で『マリ・クレール』の読者だったわたしの妻さえ独身時代に買ったという代表作『ジュ・ウヴェ』"JOU OUVE" が、つい最近、ライスを通じて国内リイシューされるまで廃盤だったという事実に時代の流れを感ぜずにはいられない。マラヴォワの音楽はバブルの時代と感応しすぎたがためにいったん人びとの記憶から消し去られる必要があったのかもしれない。 ブームが過ぎて15年ぐらい経った04年ぐらいからだろうか、かつてのワールド・ミュージックの名盤や話題盤がちょこちょことリイシューされているのに気づいた。このことには、わたしのような“ニューアカ”新人類世代にすこし金銭的な余裕が出てきたことと、ブームをリアルタイムで体験していない若者層が新しいリスナーになったことが関係しているように思う。ようやくバブルの呪縛が解けて、これらの音楽を客観的に見つめ直すことができるようになったということなのか。ちなみに、わたしはこの現象を“ワールド・ミュージックの懐メロ化”と呼んでいる。 マラヴォワをとりあげようと思ったのは、06年にフランスのレーベルFREMEAUX & ASSOCIES から発売されたMANO ET LA FORMATION MALAVOI "PREMIERS ENREGISTREMENTS(1969)" 『マラヴォワ誕生』がきっかけだった。このCDには、存在さえはっきりしていなかった69年のデビュー録音を中心にかれらの最初期のレア音源が収録されている。 それまでは長いこと、77年にDISQUES VACANCES から発売されたLP"MALAVOI" がかれらのファースト・アルバムとされていた。02年には"L'AUTRE STYLE 1975-1982"が『マルチニーク 1975-1982』としてサンビーニャから国内配給されたことで、さらに2年余り遡れることがわかった(ただしデータの裏づけは不明)。これら70年代なかばの録音はヴァイオリン奏者のマノ・セゼールが脱退したため、リーダーがピアノ奏者のポロ・ロジーヌ Paulo Rosine に代わった直後の第2期のものである。 ちなみに第2期は、マラヴォワの代名詞というべきヴァイオリンがわき役にまわり、サックス、トロンボーンとパーカッションが前面に出ている。それらは流麗でエレガントなかれらのイメージとはおよそかけ離れた、コンパ、カダンス、メレンゲ、サルサ、グァヒーラ、グァグァンコー、ボレーロなどの影響を受けたジャズ・テイストのホットな演奏である。ポロによるジャジーで力強いピアノとエレピ、マルチニークの田舎の音楽シューヴァル・ブワの第一人者デデ・サンプリ Dede Saint-Prix によるワイルドなパーカッションのプレイは聞きもの。 『マラヴォワ誕生』のライナーノーツによると、第2期の活動期間は75〜78年の約4年間で、81年にヴァイオリンを前面に立てた楽団として活動を再開するまで3年間、雌伏したとされる。このCD収録曲にはどれもホーンズがはいっていることから、録音年は75〜78年とみるべきだろう。クリスティアン・ド・ネグリ Christian de Negri 1挺のみのヴァイオリンではメリハリに欠け、全体に輪郭のぼやけた印象があるが、マラヴォワと意識さえしなければ、これはこれで聞かせる内容ではある。 第2期がこんな演奏だっただけに、『マラヴォワ誕生』で「マラヴォワがはじめからマラヴォワだった」ことのショックは大きかった。マルチニークの伝統的な音楽を土台にして、ヴァイオリンを中心とした華麗なアンサンブルと軽やかなリズムによってビギンを現代風に表現する独自のスタイルはこのとき、早くも完成されていたのだ。たしかに80年代の全盛期のような緻密な編曲や高度な演奏力とまではいかないが、基本的な部分はほとんど変わっていない。 ところで、グループ名の“マラヴォワ”とはサトウキビの一種の名まえで、69年のレコード・デビューにさいして命名された。その前身は“メリー・ラッツ”といって、63年にクラシック音楽学校でヴァイオリンを学んでいたマノ・セゼールとクリスティアン・ド・ネグリが近所に住むパーカッション奏者のドニ・ダンタン Denis Dantin らを誘って結成したチャランガ編成のダンス・バンドだった。その後、ヴァイオリン担当としてジャン=ポール・ソイーム Jean-Paul Soime が参加している。 チャランガとは、フルート、ヴァイオリン数挺、リズム・セクションを標準とするダンソーンやチャチャチャなど、キューバ音楽の優美でマイルドなダンス音楽を演奏するための楽団編成をいう。 当初はフルートもあり、キューバのチャランガ楽団、オルケスタ・アラゴーンをまねた音楽を演奏していたが、65年ごろからマノのアイデアでマルチニークの伝統的な音楽を取り入れるようになったという。のちのリーダー、ポロ・ロジーヌがグループに参加したのはこの時分と思われる。 マラヴォワより以前、ビギンやマズルカを最初に世界に知らしめたのは、マルチニーク出身で30年代を中心にパリで活躍したクラリネット奏者アレクサンドル・ステリオ Alexandre Stellio である。それは、ステリオのクラリネットが奏でる主旋律にトロンボーンとヴァイオリンがオブリガートを付けて、チェロ、バンジョー、ピアノなどが2/4拍子系のシンプルなリズムを刻むというディキシーランド・ジャズの影響を受けた集団即興のようなスタイルであった。 パリでビギンは、キューバのルンバと融合しながら完成度を高め、40年にヒトラーによってパリが陥落するまで黄金時代を築いた。キューバ出身のギター奏者ドン・バレット Don Barreto 楽団やそのメンバーだったクラリネット奏者フィリベルト・リコ Filiberto Rico のリコズ・クレオール・バンドもルンバとともにビギンをレパートリーにしていた。 第二次大戦後、ビギンはふたたび人気を盛り返した。この時代の代表的なミュージシャンとして、クラリネット奏者のサム・カスタンデ Sam Castendet やサックス奏者のロベール・マブネイ Robert Mavounzy がいる。ここでは、小アンティル諸島フランス海外県グァドループ島の出身で、フランスのハリー・ベラフォンテと呼ばれたジル・サラ Gille Sala が50年代のパテ/EMI音源から選曲したCD2枚組コンピレーション "ANTILLAISEMENT VOTRE… BIGUIES-SALSA (SUCCES DES ANNES 1950-1959)" をあげておこう。カスタンデやマブネイのように戦前のスタイルを継承発展させたオーセンティックな演奏から、ジル・サラのようにカリプソ風、ルンバ風、ボレーロ風など、よりポップに味つけされたナンバーまで多様化したビギンを味わうことができる。 ところで、60年にアフリカ円卓会議に随行してヨーロッパへやって来たベルギー領コンゴのグラン・カレとアフリカン・ジャズを積極的にバックアップしたのは、かれらの歌と演奏に感激したジル・サラだった。ちょうど南アからアメリカへやって来た若き日のミリアム・マケーバの後見役をベラフォンテが買って出たのと似たような構図だ。ジルの甘くセクシーな歌声を聞いていると、なるほどルンバ・コンゴレーズと通じるところがある。 ビギンで興味深いと思うのは、歌とおなじぐらい器楽演奏に比重が置かれていることである。これはビギンがジャズの強い影響下にあったことを物語るものである。もちろん、マラヴォワも例外ではなく、ソロ・パートにもウェイトが置かれていた83年ごろまではジャズ・テイストが濃い。 しかし、マラヴォワの独創性はなんといっても4挺のヴァイオリンとチェロとが織りなすオーケストレーションにある。 『マラヴォワ誕生』の解説でジャン=ピエール・ムーニエは、“ビギンの父”ステリオも初期においてはヴァイオリンやチェロを使っていた点を挙げ、マラヴォワの楽器編成はその伝統を汲んだものであると指摘する。しかし、ステリオ楽団での弦楽器の使い方はあくまでもポピュラー音楽の流儀に乗っ取ったシンプルなものだったのにたいし、マラヴォワはクラシック音楽の流儀にもとづく複数のヴァイオリンによる緻密なアンサンブルであるのが特異な点だ。 日本でもクライスラー&カンパニーのようにクラシック畑出身の音楽家が、ポピュラー音楽とクラシック音楽との融合を試みることはよくあるが、ほとんどの場合、上品ぶった大衆迎合趣味の域を出ていない。マラヴォワは、“洗練”によってかえって“野性”を引き出し、モダナイズされた民俗的伝統の再生に成功した奇跡的なケースといっていいと思う。 マルチニークには、ビギン以前に、マズルカ、ポルカ、クァドリーユ、ヴァルスといったヨーロッパ起源のダンス音楽が伝わっている。これらは大ざっぱにいうと、都市部ではサロン音楽として、田舎では民俗音楽(とその流れを汲んだシューヴァル・ブワ)として浸透していった。 マラヴォワは、たんにポピュラー音楽とクラシック音楽との融合を試みたのではなく、両者の区別がはっきりしていなかった時代の音楽を現代風に再現しようとしていたとわたしには思える。 だから、カリブとヨーロッパ、伝統と現代、ポピュラー音楽とクラシック音楽などという単純な二項対立では説明しきれない複雑な入れ子構造になっていて、これこそ、あの独特のマラヴォワ・マジックの秘密なのではないか。 ところで、キューバ音楽、サルサ、コンパ、ジャズ、クラシック、伝統音楽のほかにも、かれらが強い影響を受けたのがブラジル音楽である。最大のヒット曲とされる'CARESSE-MOIN' はボサノヴァ調だし、最初のヒット'LA FILO' はノルデスチ(ブラジル北東部)の伝統曲からポロがメロディを拝借したものといわれている(ともに『ベスト第一集』、および『究極のベスト!』に収録)。『ジュ・ウヴェ』収録の'LA CASE A LUCIE' はサンバ風だ。こうしてみると、マラヴォワのポップなセンスはブラジル音楽に負うところが大きいように思えてくる。 ここまで意識して避けてきたわけではないが、ズークにふれずじまいだった。ワールド・ミュージック・ブームの火付け役は80年代なかばにパリで生まれたフレンチ・カリビアン音楽ズークだった。代表格はもちろんカッサヴだ。シンセや打ちこみを駆使した陽気なノリとベタな歌謡曲路線が受けて世界中でブレイクしたが、音楽評論家の意見は賛否両論だった。そこで、ますます大衆迎合的になっていくズークへの反発として、伝統志向のマラヴォワやカリに脚光が当てられた側面はたしかにあったと思う。 しかし、他方でマラヴォワの音楽もズークで括ってしまおうというムードもあった。その先導役がCBSソニーだったと思う。カッサヴも、マラヴォワも、カリもソニーの傘下だったから、マーケティング戦略上、そうするのが都合がよかったのだろう。それにしても「情熱と優雅さは、恋にかかせない……」(LD帯より)なんて恥ずかしいキャッチコピーに惹かれてだれが買ったと思う!? ポロ・ロジーヌも、硬派の音楽雑誌や評論家たちも「マラヴォワの音楽はズークではない」としきりと強調していた。いま聞くとマラヴォワの音楽がズークとちがうのは明白なのだが、当時はまだフレンチ・カリビアン音楽がものめずらしかったものだからクレオール語で歌われてさえいればみな似たように聞こえた。 どうやら「マラヴォワはズークとして注目され、ズークでないことで高く評価された」というのが真相のようだ。 最後に主要なアルバムについてふれておこう。ただし、来日記念盤として出たが評判がよろしくなかった『スーシュ』(89年)も、ポロの遺作となった『マティビ』(92年)からあとの3枚もわたしは持っていないのでこれらについては論評を控えます。 まず、88年の『ジュ・ウヴェ』だが、これは音楽監督としてのポロの手腕が最高度に発揮されたトータル・バランスにすぐれたアルバムといえる。約6年間、在籍した看板歌手のラルフ・タマール Ralph Thamar が脱退したにもかかわらず、そのダメージをまったく感じさせない。 各曲3分台〜5分前後と収録時間がコンパクトなため、ソロ・プレイよりも緻密に練り込まれた曲構成の巧みさに耳が行く。 たとえば、'BELLE DE NUIT" では、3拍子の優雅なヴァルス(ワルツ)からさりげなくハチロクのリズムに移行するあざやかな手並み。'LEGEND'では、ノルデスチ音楽バイオーン(バイヨン)を思わせるシンコペートする2拍子系の早いリズムと、弦楽奏の優美に舞うリフレインとのコントラストの見事さ。また、'CYCLONE'では、歌詞にもアレンジにもキューバ音楽チャチャチャを援用しつつもチャチャチャに染まらずマラヴォワ流を貫いてみせる。 また、ポロ作のヒット曲'LA FILO' が'PHILOMENE' として、『マラヴォワ誕生』に収録されていた初期の代表曲'NON PA FE CA ALBE' が'ALBE' としてリメイクされるなど、このアルバムを実質的な世界デビュー盤としてレコーディングに臨んだであろうポロの強い意気込みが感じられる。'PHILOMENE' はポロのピアノ・ソロがフィーチャーされたオリジナルと比べるとコンパクトにまとめられ物足りない気がするが、'ALBE' のほうは音の厚みが増し華麗にゴージャスに生まれ変わった。 じつは全11曲中、'LA CASE A LUCIE' と'APRE LA PLI' の2曲はLPには収録されておらず、CD化にさいして86年のアルバム"LA CASE A LUCIE" から追加されたもの。前述のように'LA CASE A LUCIE' はサンバ風、'APRE LA PLI' はノルデスチ風。リード・ヴォーカルがラルフ・タマールである点を除けば他の曲との違和感はまったくない。 むしろ、マリンバを模したシンセ、スラップベース(チョッパーベース)、ヴァイオリン群などがシンプルなテーマを手を代え品を代え反復するラストのインスト曲'BLEU ALIZEE' のほうがどこか坂本龍一を思わせて異質な印象を受ける。 今回、『ジュ・ウヴェ』をひさしぶりに聞いてみて、女声コーラス、アルト・サックス、ベースの使い方をはじめ、随所に悪い意味でのオシャレっぽさやフュージョンくささが顔をのぞかせているものの、ベタに陥るぎりぎりのラインで踏みとどまっているところにこのアルバムのおもしろみがあると思った。 マラヴォワがヴァイオリン4挺に、オルケスタ・アラゴーンをヒントにしたというチェロを加えたホーンレスの編成にした第3期がスタートしたのは81年のこと。そして、プロダクション3Aと契約して同年発表したLPをそのままCD復刻したのが"LA BELLE EPOQUE"『ラ・ベル・エポック』である。ラルフ・タマールが歌手として参加したのもこのアルバムから。全6曲中5曲がポロのオリジナル作品で、残る1曲はステリオ作のマズルカ'TI CITRON'。マラヴォワがステリオをカヴァーした記念すべき第1作にあたる。まだ、全体に未完成で粗削りなところがあるものの、ヴァイオリンを前面に立て伝統的な音楽をとりいれるという路線はここに整った。 そして、わたしが『ジュ・ウヴェ』以上に高く買っている『ベスト第一集』と『同第二集』へと続く。オルター・ポップから国内配給されたこの2枚の編集盤は、GDプロダクションから82年と83年に発売された2枚組LP2タイトルと85年発売のLP1タイトルの計3タイトルLP5枚分を音源とし、全20曲中19曲を収録している(海老原政彦さん作成のリストによる)。 CDの配給元はフランスのソノディスクだが、残念ながら倒産のため現在は廃盤。これに代わるのがCREONの発売でライスから国内配給されている2枚組『究極のベスト!』(CRR-3201)である。『ジュ・ウヴェ』の収録曲も含まれているみたいだが全24曲中2/3ぐらいは2枚のベスト盤の収録曲が重なると思う。 『第一集』には、'LA FILO'、'AMELIA'、'CARESSE-MOIN' といった代表的なヒット曲が網羅されている。また、ステリオ作でカリも『ラシーヌ』でとりあげたビギンの名曲'CONVERSATION' のリメイク、ヴァイオリン奏者がクリスティアン・ド・ネグリがめずらしく作曲したヨーロッパ色の濃いダンス音楽クァドリーユによる'QUADRILLE C'、3拍子と4拍子系のリズムが重なるポリリズミックなマノ・セゼール作の'PASSILLO MAT'NIK' など、ヴァイオリンが大活躍する華麗で軽快なインスト曲の充実ぶりも特筆すべき。 アルバム冒頭の'LA FILO' は、一度聞いたら忘れない楽曲のよさもさることながら、間奏部にはさまれるポロのメリハリの効いたピアノ・ソロがすばらしい。ウッド・ベースも操るベース奏者ジャン=マール・アルビシーJean-Marc Albicy 同様、ポロが基本的にジャズ畑のプレイヤーであることがよくわかる。この曲から上記インスト3曲までの流れがあまりにもすばらしすぎて、後半の5曲がやや霞んでしまっている。 といっても、マノの作でタマールがしっとりセクシーに歌うボレーロ'CINELLO O' や、ブラジルの弦楽器バンドリンのような音色がフィーチャーされるポロ作の'MARINELLE' など、心動かされる楽曲ばかりだ。ただし、ヒット曲'CARESSE-MOIN' については個人的にボサノヴァの感傷癖が苦手なのでコメントは差し控えよう。 ヒット曲中心の『第一集』にたいし、伝統的な曲を中心に選曲されたといわれているのが『第二集』だ。 'GRAM E GRAM' は、ポロによる緻密なアレンジと、スウィンギーなピアノ・ソロが堪能できる傑作ナンバー。11分14分という収録時間の長さをまったく感じさせない。続く'ZOUEL' もまったく同様で、ポロのピアノ、ジャン=マールのベース、ドニ・ダンタンとニコル・ベルナールNicol Bernard のパーカッションによるインタープレイに思わず息を呑む。これらの曲でヴァイオリン群はあきらかに引き立て役にまわっている。 ところが、マノ・セゼール作のアップテンポで旋回的な欧風ダンス音楽'QUADRILLE M' では一転してヴァイオリンが大活躍。そのせいであまり目立たないが、よく聞くと超高速で細かく刻まれるパーカッションのプレイもすさまじい。これこそ、まさにマラヴォワの独壇場。 マラヴォワの楽曲中、もっとも複雑で緻密なアレンジが施されているのは、おそらくポロ作の'ANTOINISE' ではないだろうか。スタジオ録音としては最長の11分20分におよぶこの曲は、テンポやメロディがめまぐるしく変化するドラマチックな構成で、マルチニークの自然と文化がサウンドに織り込まれた、さながら一編の交響曲のようだ。 'BAVAROISE'、'MALAVOI'、'GUADELOUPEENNE' の3曲はいずれも伝承曲にポロがアレンジを施したもの。'MALAVOI' は、文字どおり楽団のテーマ音楽といえるもので、マルチニークの香り濃厚な名曲名演。'GUADELOUPEENNE' は、93年のアルバム『マティビ』で'LA GWADLOUPEEN' としてタニア・サンヴァルに歌わせたのとおなじ曲。ただし、こちらはインスト。 ここまで、冒頭の'GRAM E GRAM' を除く6曲は83年のダブル・アルバムから採られている。マノ本人がこのアルバムを自分のフェイヴァリットと語ったように、楽曲構成と演奏力ともに、密度の濃さでは最高峰をきわめたアルバムといってよい。本当にすばらしい。 このアルバムから『第一集』収録の'CARESSE-MOIN' のようなヒット曲が生まれ、これが契機となったのか、続く85年のアルバムでは、職人的なジャズ・テイストが薄らいで、よりブラジル音楽寄りのポップな路線に軌道修正した印象を受ける。 『第二集』の後半3曲'TI COLIBRI A'、'MOIN REVE'、'BONA' はその85年のアルバムから。これらを聞くと、ポロ作の'TI COLIBRI A' はブラジル=サンバ風、マノ作の'MOIN REVE' はキューバ=ボレーロ風。どちらもこの上なく透明でエレガントなところが心憎い。 マノ作の'BONA' は後述するゼニットでのライヴがそうだったように、いかにもフィナーレにふさわしいパーカッションをフィーチャーした楽しく陽気な曲調。かれらが大衆受けをつよく意識するようになったあらわれなのか。それは折りしもズーク人気が盛り上がりを見せた時期でもあった。 そして、ついに86年、パリのレーベル、ブルー・シルヴァーと契約、初のパリ録音による"LA CASE A LUCIE" が発売される。1曲の演奏時間は3分台から5分前後と短く、ズーク調のインスト'ATLANTIK' を除けば、ラルフ・タマールのスウィートな歌をフィーチャーした全7曲構成。このうち、'LA CASE A LUCIE' と'APRE LA PLI' の2曲は前述のようにCD『ジュ・ウヴェ』に再録。また、87年のゼニットでのライヴ盤『ライヴ・アット・ゼニス』"MALAVOI AU ZENITH" ではこの2曲に加えて'SPORT NATIONAL' と'APARTHEID' の計4曲が採り上げられている。ポップでカラフルな作りだが深みには欠ける。 『ライヴ・アット・ゼニス』は、当初、輸入盤で紹介され、これが話題を呼んで日本でマラヴォワ・ブームが起こるきっかけとなった。日本盤は90年に発売され、前年にビデオ(LD)が先行発売された。日本盤は、オリジナルCDでは収録時間の関係で割愛されていた'APRE LA PLI' と'XIOMARA' の2曲をミニCDに追加した2枚組完全盤。ビデオ(LD)は5曲がCDと重複するが、ソロ・デビュー前のエディット・レフェールがうたう'CARESSE MOIN'、'LOUP-GAROU'、'LA CASE A LUCIE' の3曲はCDに収録されていない。 わたしは日本盤CDとLDを持っているので、今回のレビューのためにCDだけでなく、ずっと眠らせてあったLDプレイヤーを出してきて映像のほうも観てみた。ホーン・セクションや女声バック・コーラスも参加し、エレガントというよりはサルサに近いセンティメントを帯びたダンサブルなノリである。音楽だけならスタジオ録音のほうが断然好きだが、映像付きならかなり楽しめる。来日公演に行こうかどうか迷ったすえに、結局、行かなかったことを悔やんだ。 ゼニットでのライヴ盤のつぎが『ジュ・ウヴェ』で、そのつぎがわたしが持っていない『スーシュ』"SOUCH'"、そして92年に結成20周年記念盤として3年ぶりに発表された新作が『マティビ』"MATEBIS" である。マノ・セゼールは体力的な問題から90年に引退したため不参加。リーダーのポロ・ロジーヌは病を押しての参加だったがアルバム完成直後の93年1月にガンのため還らぬひととなった。45歳だった。 日本盤はワールド・ミュージック・ブームが終焉した93年にソニーから発売された。ラルフ・タマール、エディット・レフェール、タニア・サンヴァル、カッサヴのジョスリン・ベロアール、カリなど、豪華なゲストを迎えた本盤は『マラヴォワ誕生』解説のムーニエによれば「マラヴォワのアルバム中、おそらくもっとも完成度が高い」とのこと。ゲスト歌手たちのヴォーカルに焦点が当てられ、ヴァイオリン群は一歩下がってサポートに回っている。そのため、コンパクトでキャッチーな歌曲でそつなく構成されたコンピレーションといった印象だ。 クレジットをみると、アレンジはマノではなくマリー・ロジーヌとある。マノの病状はよほどすぐれなかったとみえて、おそらく妻の手を借りたのではないか。「ズークではない」ことのプライドが売りだったマラヴォワも、ここに来てついに一線を越えてしまったというのが正直な感想だ。 ポロの死後、マラヴォワはジャン=ポール・ソイームを新たなバンド・リーダーとして3枚のアルバムを発表したが、99年の"FRENCH KANN" を最後に活動を停止したという。 こうしてみると、マラヴォワはまさしくバブルのなかで人気が沸騰し、バブルの終焉に歩調を合わせてシーンから消えていったのがわかる。もっともバブル景気は日本独自の現象。先にわたしは、マラヴォワとバブル景気との共通項は「祝祭性」にあるといったが、世界的にみればそれは東西冷戦構造の終結からくる解放感と未来への楽観ムードと重なる。そして、ユーゴスラビアをはじめ、世界各地で民族紛争が頻発するようになったころ、ポロの死とともにマラヴォワも第一線から遠ざかっていった。世界にふたたび、マラヴォワの登場を求める時代が来るだろうか? |
||||||||||||||||
|
(5.8.07) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
前の画面に戻る |
||||||||||||||||