| World > Latin America > Caribe > Haiti | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Artist | ||||||||||||||||
|
TABOU COMBO |
||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
|
SUPER STARS |
||||||||||||||||
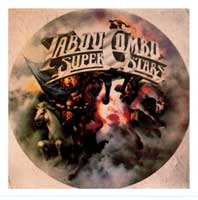 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Review |
||||||||||||||||
| 60年代なかば、ハイチでは、ヌムール・ジャン・バチストによって確立されたコンパ・ヂレクトの流れを汲みながら、エレキ・ギター主体の小編成バンドによる演奏スタイルが流行するようになった。これを「ミニ・ジャズ・ムーヴメント」と呼び、シュレ・シュレ(のちのスカシャ#1)とともに、その中心的な担い手となったのが現在も活動をつづけるベテラン・バンド、タブー・コンボである。 タブー・コンボは、1966年ごろ、アルベールとアドルフのチャンシー兄弟を中心に結成された。若い世代の心情をストレートに表現したサウンドは、ヌムール・ジャン・バチストやウェベール・シコーなど、ビッグ・バンド編成によるそれまでの優雅なコンパとは一線を画すモダンでシャープな感性を宿していた。そこにはロックの影響があったのはいうまでもないが、それと同時に、コンゴ民主共和国(旧ザイール共和国)のルンバ・コンゴレーズ(いわゆるリンガラ音楽)の影響もみられるという。 60年、ベルギーから独立したコンゴは、グラン・カレとアフリカン・ジャズやフランコとO.K.ジャズなど、多くのアフリカン・ポップスのパイオニアたちを輩出した。その音楽は、フランス語を教えるなどの目的でコンゴへやって来たハイチ人たちの手によってハイチへもらたされたという。真偽は定かでないが、複数のギターが甘いトーンで連綿と反復されるスタイルには、なるほどリンガラ音楽との親近性が感じとれる。 71年、デュヴァリエ政権の圧制から逃れて、活動拠点をニューヨークへ移すが、そこでヘイシャン・ミュージックの金字塔といわれる傑作『ニューヨーク・シティ』"8TH SACREMENT"(MINI MRS D1044(US) / Pヴァイン UPCD-9(JP))を74年にリリース。故郷を離れニューヨークで貧困にあえぎながら暮らしていたハイチ人たちのあいだで大ヒットを記録した。ここでは、管楽器を使用せず、モダン・コンパの基本形である独特のタメのある横ノリで、アコーディオンとリード・ギターを前面に押し出した“泣き”のあるダンス・ミュージックを展開している。 翌75年の"THE MASTERS"(Pヴァイン PCD-2203(JP))は、ジャン・クロード・ジャンが一時的に脱退したため、リーダーはリード・ギターのバドゥ・パスケットに交代したが、『ニューヨーク・シティ』で確立したモダン・コンパ路線をさらに発展させ、ギターを前面に押し出したかれらの作品中、もっともスピーディかつ先鋭的なロックっぽいアルバムになった。ここからシングル・カットされた「インフラシオン」'INFLACION' は「ニューヨーク・シティ」に次ぐヒットとなった。 その後、ベースのアドルフェ・チャンシー(兄アルベールは渡米前に脱退している)がリーダーになると、バンドはホーン・セクションを導入しソウル〜ファンク路線を押し進めるようになる。 78年に発表された"THE MUSIC MACHINE"(MINI MRSD1070(US))は、EW&Fを意識したチープなピラミッドの張りぼてをバックに、悪趣味なスペース・ファッションに身をつつんだおっさん風のジャケットがおちゃめだ。ブーツィ・コリンズのような“洗練された悪趣味”ではなく、あくまでも“ダサイ悪趣味”というのがミソ。でも、このアルバム、ディスコ調の'LET'S DANCE' を除けば、コンパとソウル〜ファンクが見事に融合した、バンドとしての一体感の点では格段の進歩をみせた傑作だと思う。なかでも、コール・アンド・レスポンスの応酬で聴衆をグイグイとひきこんでいく3曲目の'TABOU MANIA' とラストの'MA BOUYA' の昂揚感はすばらしい。 79年には、自らのレーベルを設立。同レーベルからリリースされた86年までの7枚のアルバム(87/88年の"QUITEM FE ZAFEM"を加えると通算8枚リリース)は、タイトルがすべて"SUPERSTARS"なのでややっこしいが、どれをとっても平均以上の高水準の作品ばかりだ。ジャケットは以前にも増してヤボッたいが(CDの背表紙はすべて'TABOU COMBU'と誤植してある ! )、音楽的にもっとも充実していた時期なだけに、どれか1枚だけとりあげるというのはたいへんむずかしい。あえてというなら、代表曲'BAISSEZ-BAS'、'NEW YORK CITY' の再演、ヌムール・ジャン・バチストへのオマージュ曲を収めたCHANCY CRCD-7985も捨てがたいが、聴いた頻度の多さから84年リリースの本盤をとりあげることとした。 この時期のものには、かならずといってよいほどディスコ路線の捨て曲が1曲は入っているのだが、このアルバムにかぎり、全4曲すべてがコンパというのがありがたい。ホーン・セクションの切れ味は抜群にすばらしく、元気いっぱいの(合いの手のような)コーラスをバックに、ロジャー・ユジェーンの力強く伸びやかな歌声がいっそう輝きを増している。まろやかなトーンでシャープなカッティングを聞かせるジャン・クロード・ジャンとエリ−ゼ・ピロンヌーのギターのカラミを聴いていると頭がクラクラしてくる。チョッパーにも挑戦しているリーダー、チャンシーのベースもファンキーだ。 ラストの'BOLERO' では、なんと、早くもラップに取り組んでいる。ちなみにドミニカの怪人ウィルフリード・バルガスは、このラッピング・パートをそっくりいただいて'EL JARDINERO' というタイトルで演奏している("LO MEJOR DE WILFRIDO VARGAS" (KAREN CDK-503) または"LOS ANOS DORADOS" (KAREN CDK148) などで聴くことができる)。それにしても、このバンドの消化力の旺盛さには頭が下がる(それをさらにパクるウィルフリードには及ばないとしても‥‥)。それでいながら基本はあくまでもコンパというところが心憎いではないか。 これらのアルバムのあと、当時流行していたズークを取り入れた通称"QUITEM FE ZAFEM"(ESPERANCE CD8055(FR))と日本でも発売された『アンチル』"AUX ANTILLES" (ZAFEM CD8056(FR) / オルターポップ FCPCD01(JP))を発表。カリブ的な視点に立った音楽志向が注目を集めるが、いま聴くとシンセやうちこみなど大幅なテクノロジーの導入が、かえって本来の熱い持ち味を殺してしまっているように感じられる。まもなく、アドルフェとジャン・クロードが脱退。それでも90年の来日コンサートは、わたしがこれまで観たなかでもっともエキサイティングなステージだった。あとにもさきにも、日比谷野音も含め、すべての東京公演に足を運んだのはタブー・コンボだけである。 |
||||||||||||||||
|
(11.27.01) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
前の画面に戻る |
||||||||||||||||