| World > Africa > Democratic Republic of the Congo | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Franco et O.K. Jazz (1956-89) | ||||||||||||||||
|
Madilu Bialu 'System', vocal(1980-) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Artist | ||||||||||||||||
|
MADILU ET SON ORCHESTRE TOUT PUISSANT SYSTEM |
||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
|
LE TENANT DU TITRE |
||||||||||||||||
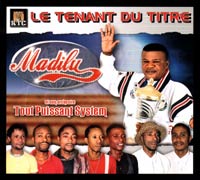 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Review |
||||||||||||||||
| 80年代以降のO.K.ジャズを特徴づけるサウンドに、わたしがフランコの「ぼやき節」と名づけたスタイルがある。ギターがシンプルなパターンをくり返すなか、読んで字のごとく、フランコが例のバリトン・ヴォイスで説教を滔々と垂れまくるというやつだ。 当初は、フランコによる“ぼやき”の節目節目にキャッチーなコーラスのリフレインがはさまれるのが通例だった。牧伸二でいうと「あ〜んああ、いやんなっちゃった。あ〜んあああ、驚いた」をコーラスが担当する。 フランコの一人芸だった「ぼやき節」を相方との掛け合い芸に仕立てた最初が83年発表の'NON' (SONODISC CDS 6851収録)だった。このとき、相方に選ばれたのがマディル・システム。これが大当たりして、以後、フランコとマディルのコンビによって、'TU VOIS? (MAMOU)'(同CDS 6853収録)、'MARIO'、'LA VIES DES HOMMES' (共にESPERANCE/SONODISC CD 8461収録)といった数々の「ぼやき節」の名演が生まれた。 ふたりの関係は、万歳でいうところの太夫(たゆう)と才蔵(さいぞう)にあたる。これがぼけとつっこみの対話として現代の漫才につながっている。代わる代わる口上をのべ、あいづちをうったり、ハモったり、音楽的なノリにのせて二人が一つの話を進めるというところは万歳とそっくりだ。旋律と反復と対話形式は、古今東西問わずメッセージを伝達するもっとも有効な方法なのだ。 マディル・システム Madilu Bialu 'System'は、69年、19歳でデビューすると、パパ・ノエルのバンブーラ Bamboula、サム・マングワナのフェスティヴァル・デ・マキザール Festival des Maquisards などを渡り歩いたあと、バクバ・マヨピ Bakuba Mayopi を経て、76年、元オルケストル・ベラ・ベラ Bella Bella のソキ・ヴァングのサポートで自分のグループを結成。オルケストル・パンバ・パンバ Pamba-Pamba と名のったグループは、まもなくマディル・システムと名称変更。バンドが解散したのちは、バンド名がそのままかれのステージ・ネームになった。 その後、タブ・レイのアフリザに2年間在籍するも伸び悩み、80年にTPOKジャズに加入。フランコとの出会いによって、遅咲きの才能はようやく花開いた。 89年、フランコが世を去ると、シマロをリーダーに、ジョスキーとマディルがわきを固めるというトロイカ体制でTPOKジャズは維持されることになった。フランコ死後のTPOKジャズのアルバムを聴いていつも思うのは、シマロやジョスキーの個性は生きていても、マディルの存在感がいまいち薄いということ。 シマロやジョスキーとちがって、マディルのコンポーザーとしての力量はたいしたことないとわたしは思っている。マディルのハスキー・ヴォイスが最高に生きてくるのは、フランコが書きフランコとがなる「ぼやき節」をおいてほかはない。マディルとフランコは一蓮托生なのだ。 シマロのTPOKジャズは長く続かなかった。92年と翌年にロラ・シェケン Lola Djangi 'Checain'、エメ・キワカナ Aime Kiwakana、ジョー・ンポイ 'Djo' Mpoyi Kaninda の3人のシンガーが相次いで死去。93年には、シマロらメンバーとフランコの親族との確執が表面化。TPOKジャズというグループ名を使えなくなったシマロらは、94年新春に「O.K.ジャズの子どもたち」を意味するバンド、バナO.K Bana OK を旗揚げする。 マディルはというと、シマロの側に与しなかった。シマロを三沢光晴とすれば、マディルは全日本プロレスに残った川田利明というところ。マディルは新たなメンバーとTPOKジャズを再開させるべくリハーサルしたが6ヶ月で断念。マディルはソロ歌手として本格的に活動をはじめる。 直後にマディル・マルチシステム名義で発売された"OPERATION QUATRE" (CASCADE CP568) が典型だが、シンセやうちこみを多用したきらびやかだがチープなサウンド・プロダクトで、どのアルバムもマディルの個性が生かしきれているとはいいがたい。 あえてというならTPOKジャズ在籍中にジョスキー、リゴ・スターと組んだ4曲と、カルリート、マラージュと吹き込んだ4曲からなる編集盤 JOSKY KIAMBUKUTA & MADILU SYSTEM "LES DEUX GRANDS NUMEROS DANS DESTIN"(NGOYARTO NG041)だろう。しかし、悩みに悩んだあげく最終的に選んだのが、2004年にリリースされたこの最新盤である。理由は別にあるのだ。 なによりもこのグループ名。マディルとオルケストル・トゥ・ピュイサン・システムである。TOUT PUISSANT(全能の)は、フランコがO.K.ジャズに冠した王者の証。さらに「タイトル・ホルダー」を意味する自信ありげなアルバム・タイトル。つまり「オレさまこそ偉大なる巨匠フランコの真の後継者」といいたいのだ。 添付のブックレットには、マディルを囲む若手ミュージシャンたちとの集合写真が載っている。どいつもこいつもヒトクセもフタクセもありそうな悪相ぞろいで、マディル親分と子分たちといった風情だ。マディルは'NINJA' と自称していたが、むしろ'YAKUZA' と名のるのがふさわしい。 幕末期に多数あらわれた博徒・侠客たちはたいてい百姓の出。イキがってるところがかえって素朴で野暮ったいメンバーのツラをながめるにつけ、勢力富五郎一家もきっとこんなんだったろうと想像した。このたたずまい、キライではない。 ちなみにバックカバーにはダンサーだろうか、7人の女性の顔写真が載っている。これがまたおそろしくブサイクでほほえましい。 で、肝心の中味はどうなんだって? フランコの後継者を気どる大胆不敵なまでの自信とはうらはらにまことにお寒い内容といわねばならない。全10曲トータル約80分。全編通して聴いたのは今日がはじめてだった。 マディルはTPOKジャズにおけるフランコのつもりでいる。自分が歌うとき以外は、メンバーのソロやコーラスの節々に、ことあるごとに掛け声やら気合いを入れて、この音楽を仕切るのは自分であることを誇示する。しかし、いくらなんでも五月蝿(うるさ)すぎ。そのため、かえって締まりなく散漫な印象を受けてしまう。 また、曲調も、上すべり気味のヴォーカル陣も、シンセを多用した伴奏も全体に軽すぎてマディルのハスキーな声に溶け込んでいない。気になったといえば、終盤の'LUNE DE MIEL' という曲でアコーディオンが使われていたことぐらいか。 フランコにマディルがいたように、太夫のマディルには才蔵が必要なのだ。この程度のレベルなら、なっちの盗作曲のほうが数段マシ。 |
||||||||||||||||
|
(12.10.04) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
前の画面に戻る |
||||||||||||||||