| World > Africa > Democratic Republic of the Congo | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Franco et O.K. Jazz (1956-89) | ||||||||||||||||
|
Antoine 'Papa Noel' Nedule Montswet, guitar(1978-) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Artist | ||||||||||||||||
|
PAPA NOEL |
||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
|
BEL AMI |
||||||||||||||||
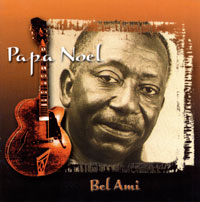 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Review |
||||||||||||||||
|
パパ・ノエル、本名 Antoine Nedule Montswet は、1940年ベルギー領コンゴ(のちのコンゴ民主共和国、ザイール)の首都レオポルドヴィル(のちのキンシャサ)生まれ。クリスマスの日に生まれたことから「パパ・ノエル」とニックネームされた。 |
||||||||||||||||
|
(12.6.06) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
前の画面に戻る |
||||||||||||||||