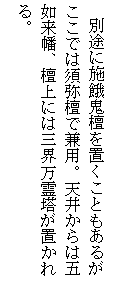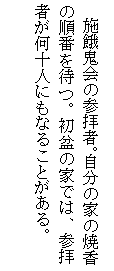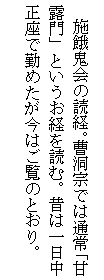年中行事
1.はじめに 2.大般若会 3.涅槃会 4.花祭り 5.お盆
5 お盆(施餓鬼会)
お盆とは、祖霊を死後の苦しみから救済するための仏事。盂蘭盆(うらぼん)とは逆さ吊りの苦しみという意味だそうです。もともとこの行事は陰暦の7月13日から15日に行われていたものですが、新暦の採用でこの日付では梅雨明け前になってしまうことから今では8月に行う地域が多いようです。このあたりでも大体は8月の行事ですが、瀬戸市や多治見市など東濃地方では7月に行われています。ちなみに「施餓鬼」は俳句では秋をあらわすのだそうです。
このお盆の行事は迎え火に始まり、送り火で終わります。「火」はご先祖様たちがあの世から帰ってこられるための灯台の役割を果たすものなのでしょう。村はずれの川原やお墓の前とか家の門口で松の根の松明が焚かれます。昔々は村はずれより外は、そのまま魑魅魍魎の住む黄泉の国へつながっていたのかも知れません。
こうして家に招き入れられたご先祖様は、お帰りになる15日の夕方まで、家人のもてなしを受けます。各家にはお盆棚が設けられて仏壇から位牌が取り出され、その前に真菰のござや蓮の葉っぱを敷き、さまざまのお供え物が並べます。このご先祖様の滞在中に寺から棚経に出向きます。この猛暑の中の棚経ほど僧侶にとってつらいものはありません。立ったり坐ったりで膝はガクガクになり声もつぶれます。それでもなんとかお盆じゅうに全檀家をまわります。
施餓鬼はこうしたお盆の行事の一環として執り行われます。最近では施食ともいわれるようになりましたが、お釈迦様の弟子のアーナンダが餓鬼道に落ちた自分の親の供養をしたのが始まりだそうです。そもそもは輪廻の思想が元になっているのでしょう。慈眼寺においては8月18日に行います。