| World > Africa > Democratic Republic of the Congo | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Artist | ||||||||||||||||
|
TIERS MONDE COOPERATION |
||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
|
BOWAYO & OMESONGO |
||||||||||||||||
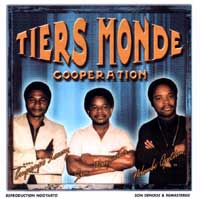 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Review |
||||||||||||||||
| ティエール・モンド・コオペラシオン Tiers Monde Coopeationは、ロシュロー(タブ・レイ)スクールの出身で、フランコのTPOKジャズに籍を置いていた3人、サム・マングワナ Sam Mangwana、“ぺぺ”ンドンベ・オペトゥム 'Pepe' Ndombe Opetum、エンポンポ・ロワイ Empompo 'Deyesse' Loway を中心に83年に結成されたグループ。まもなくマングワナが抜け、代わっておなじくTPOKジャズにいたジョー・ンポイ 'Djo' Mpoyi Kaninda とジャト・ルコキ Diatho Lukoki が加入した。 本盤は、レアで質の高いコンゴ・ミュージックの古典をリリース続けるフランスのレーベル、ンゴヤルトの記念すべき100枚目として発売された(といっても欠番もいくつかあるようだ)。マングワナが参加した前半4曲は83年発売のLPから、ジョーとジャトが参加した後半4曲は(おそらく)84年と85年に発売された2枚のLPから2曲ずつ採られたもの。 メンバーのなかでいちばん有名なサム・マングワナは「伝書鳩」とあだ名されたように、ひとところに落ち着いていたことなく、グループからグループへ、国から国へとつねに転々としつづけた。 66年にロシュローのアフリカン・フィエスタ・ナショナルに参加したのを皮切りに、ヴォックス・アフリカ→アフリカン・フィエスタ・ナショナル→フェスティヴァル・デ・マキザール→フリー→TPOKジャズ→フリー(アンゴラへ)→アフリザ・アンテルナショナル→フリー(アビジャン)→アフリカン・オール・スターズ→82年のフランコとのコラボレーション‥‥というように、まさに神出鬼没。 マングワナ本人は45年キンシャサ生まれだが、かれの両親はアンゴラからの亡命者であった。そのため、かれにはいつも自分は制外者−漂泊者という意識があったという。だから、78年にアビジャン(コート・ジヴォアール)で結成されたアフリカン・オール・スターズで、リンガラ音楽の型を逸脱して、フランス語で歌い、ハイライフやディスコ・サウンドを大胆にとりいれることにもためらいはなかったはずだ。 わたしは、こういう“無節操”がキライではない。しかし、マングワナの場合は、そこに小器用さと不器用さの奇妙な混在が感じとれ、それが鼻についてしまってどうしても好きになれない。 けれども、ヴォーカリストとしてのかれは高く買っている。リンガラ音楽の歌い手にありがちの自己陶酔的でベタついた感じはなく、あくまでカラっとしていて、それでいながら哀愁味のある魅力的な声だ。TPOKジャズの詩人シマロが書いた'MABELE (NTOTU)' を稀代の名曲たらしめているのは、かれのすばらしい歌声があったればこそといえよう(FRANCO & LE T.P.O.K.JAZZ "1972/1973/1974" (AFRICAN/SONODISC CD 36538) 収録)。 本盤冒頭のマングワナが書いた'BOWAYO' は、シマロの名作'EBALE YA ZAIRE'(FRANCO,SIMARO ET LE TP OK JAZZ "1974/1975/1976" (AFRICAN/SONODISC CD 36520) 収録)や'FAUTE YA COMMERCANT'(FRANCO-SIMARO-SAM MANGWANA & LE T.P.O.K.JAZZ "1982/1985" (SONODISC CDS 6854) 収録) をほうふつさせるたおやかで叙情的なナンバー。 びんを叩いて刻まれる素朴なシンキージョ(キューバ音楽独特の5つ打ち)のリズムにのせて、メロウなトーンのギターがシンプルで美しい旋律を奏でる。そこへ「あはー」「お、めめ、ほら、きた」と、マングワナの脱力感にあふれたかけ声が乗っかってくる。このイントロですでに名演であることが保証されているといっていい。 主題部にはいると、マングワナのハスキーなヴォーカルが泣きたくなるような哀感をたたえながら、ゆったりと優美に流れていく。間奏部にエンポンポによるカリフォルニア・シャワー系のさわやかなソプラノ・サックスのソロがはさまれる。'FAUTE YA COMMERCANT' のセッションにもエンポンポが参加していたから、これにならったのであろう。後半部のサックスの透明なユニゾンもエンポンポならでは。この楽園のような音楽を聴き入るうちに、なぜかいい知れない郷愁をかきたてられる。それは、折口信夫がいうところの常世へのあこがれから来るものなのか。 “ぺぺ”ンドンベ・オペトゥムは、マングワナの脱退後、ロシュローのアフリカン・フィエスタ・ナショナルにヴォーカリストとして加入。72年にロシュローのアフリザ・アンテルナショナル(アフリカン・フィエスタ・ナショナル)を脱退すると、サックスのエンポンポをさそってアフリザム Afrizam を結成した。このバンドにマングワナはゲスト・ヴォーカルとして参加したことがある。ということは、ティエール・モンドの3人は、グループを結成する10年近く前に共演していたことになる。 75年、マングワナの後任としてTPOKジャズに加入。長くTPOKジャズのメイン・ヴォーカルの1人として活躍してきたが、ティエール・モンドを結成する直前に一時TPOKジャズを抜けていたようだ。 そのンドンベが書いたその名もずばり'TIER MONDE' は、82年にフランコとマングワナの顔合わせでおこなわれたセッションでいえば、'COOPERATION'(FRANCO/SAM MANGWANA ET LE T.P.OK JAZZ "1980/1982" (SONODISC CDS 6860) 収録)にあたるナンバー。というか、あきらかに'COOPERATION' を意識してつくられた曲というべきだろう。明るく元気いっぱいなビートにのせて、ンドンベとマングワナが和気あいあいと歌を交わしながら、3人のメンバー紹介をしていく。エンポンポのサックスもすこぶる健康的で清々しい。ちなみに'TIER MONDE' とは「第三世界」の意味。 おなじくンドンベが書いた'NGUI NGON' と'FAUX PROBLEMES' も軽快でさわやかなナンバー。コーラスによる執拗なリフレイン主体の展開といい、それにつづくンドンベの流れるようなヴォーカルといい、めくるめくギター・アンサンブルといい、ブレイクでのホーン・セクションの用法といい、これはもうオーセンティックなTPOKジャズ・サウンド。 わたしは、ティエール・モンドのキイを握っていたのはエンポンポだったとみている。エンポンポは、60年代なかばごろからいつもロシュローやフランコの周辺にいて、グループに在籍していたときでも、かれらとは一定の距離をとりながら独自のカラーを追求してきた人物(のような気がする)。 トランペットよりもサックスが好まれるコンゴのポピュラー音楽にあって、かれのサックスは流麗さや洗練度においてひときわ抜きん出ていた。70年代までは、まだジャズっぽいアーシーな面もあったが、本盤がレコーディングされた80年代になると、音がグンと軽くなってジャズというよりフュージョンに近い感覚になった。アルトとともに(アフリカではめずらしい)ソプラノ・サックスを吹く機会もふえたようだ。抜群にうまいが、アクが足りないところなど“コンゴのナベサダ”と呼ぶにふさわしい。 そして、かれにはサックス・プレイヤーの顔のほかに、プロデューサーとしての顔があった。 75年末、当時19歳のムポンゴ・ロヴ M'pongo Love と出会い、その才能に惚れ込んだかれはTPOKジャズ在籍中だったにもかかわらず、彼女の全面的なバックアップを買って出る。自身のサックスに加えて、ギターには元アフリザのボポール・マンシャミナとザイコのマヌアク・ワク、キーボードにはレイ・レマというぜいたくなサポート・メンバーを起用、ムポンゴをトップスターに育て上げた("COMPILATION MUSIQUE CONGOLO-ZAIROISE (1972/1973)" 収録)。ムポンゴとのコラボレーションは、80年代なかばまでつづいた。 本盤に話題を戻すなら、マングワナの1曲とンドンベの3曲については、これまでのリンガラ音楽(とくにTPOKジャズ)のスタイルを踏まえたサウンドであったが、エンポンポが書いた残りの4曲については、いずれも型にはまらぬポップでバラエティ豊富な内容。 たとえば、ジョーらしきヴォーカルと女性コーラスの掛けあいで歌われる'ZUNGULUKE' では、シンプルな横ノリのリズムとホーン・セクションの使い方がハイチのコンパを思わせる。間奏部でのギターとサックスのソロもあきらかにコンパを意識したもの。ただし、ズークの影響か、コンパ特有の泥くささや高揚感はなく、全体に意外とあっさりした仕上がり。 そして'CHRISTO' にいたってはレゲエ仕立て。シンセでスティール・パンの音を模したりして、トリニダードのソカのにおいもする。さらに、メロディ・ラインはキューバの「南京豆売り」風だったりする。 ラストの'ANITHA' は、前の2曲にくらべれば、オーソドックスな展開ながら、やはりどこかフツーじゃない。ハイハットが刻む細分化されたリズムはジンバブウェのチムレンガのようだし、ギターのカッティングはファンクぽかったりする。出色は後半のセベン・パート。どこまでも涼やかなギターの旋律に、サックスのユーモラスで躍るようなユニゾンが乗っかってきて、祝祭気分でしあわせいっぱいになる。 「2003年ベスト・アルバム」で本盤を選出した時点では、これらはいずれも音が軽すぎて、とるにたらない曲と思っていたが、聴けば聴くほどアレンジがものすごくよく練られているのがわかってきた。ティエール・モンドの本領は、むしろエンポンポが書いたこうした曲調にこそあるとみるべきだろう。 ファースト・アルバムをレコーディングした直後にグループを離れた「伝書鳩」は、2年半後の86年に舞い戻ってきて「ナベサダ」と組んで、今度はティエール・モンド・レヴォルシオン Tiers Monde Revolution のグループ名でレコーディングをおこなっている。 そうそう、コンゴ・ミュージックの影の仕掛人エンポンポは、フランコの死後、TPOKジャズを引き継いだシマロから、フランコ追悼コンサートのミュージカル・ディレクターを任された。かれがTPOKジャズの正規メンバーだったのは70年代なかばのごく短期間だったにもかかわらず、この大抜擢は、かれのプロデューサーとしての才能がいかに高く評価されていたかを物語っている。 しかし、コンサートの翌月にあたる90年1月21日、エンポンポは世を去った。かつての愛弟子ムポンゴ・ロヴの死から6日後のことであった。 |
||||||||||||||||
|
(4.27.04) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
前の画面に戻る |
||||||||||||||||