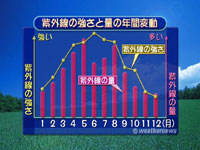|
|
|
|
|
| 1. 紫外線の種類 |
|
太陽光線は、波長によって
紫外線・可視光線・赤外線の3種類に分類されています。紫外線は波長がおよそ1nm(ナノメートル)から400nmの間の太陽光線のことで、波長の長さによってUVA、UVB、UVCの3つに分類されます。
これらの紫外線のうち、波長の短いUVBとUVCのほとんどは大気中の酸素やオゾンに吸収されてしまうため、私達が浴びる紫外線のおよそ90%から95%
はUVAです。日焼けの原因になるのはUVBですが、しわやたるみなど肌の老化の原因になるのはUVAです。地表に降り注ぐUVA量は、曇りの日でも晴れの日と大きく変わらないため、意外と厄介なシロモノなのです。
|
| 2. 紫外線の量・強さに影響する要素 |
|
| 日本の一年間の紫外線量は5月から8月にかけてが最も多く、冬の間は比較的少ないといえます。お天気に着目すると、快晴の日が一番紫外線量が多く、曇りは晴れの日の約70%、雨の日で約30%となっています。一日の中では正午近くが一番紫外線が強いので、お昼休みに外に出るときは意識的に日陰を歩くなどして日射しを避けましょう。 |
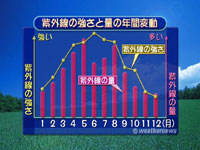 |
また、高度が300m高くなると紫外線量は4%多くなります。涼しいとつい油断しがちですが、高原や山のレジャーでも紫外線対策が不可欠です。また、紫外線の多くは上空のオゾン層で吸収されるため、オゾン量によっても地表に達する紫外線量は大きく違ってきます。日本では、春にオゾン量が多くなり、夏から秋にかけて少なくなる傾向がみられます。
緯度に着目すると、紫外線量は赤道に近いほど多くなります。例えば北緯10度のパナマの年間紫外線量は、北緯70度のノルウェーのなんと約5倍!南の島でバカンスを考えている人は、紫外線対策により一層の注意が必要ですね。
このように、地上に降り注ぐ紫外線の量は、緯度・標高・季節・天候・時間、そして上空のオゾン量・・・と様々な要素で変わってきます。ちなみに、冬の紫外線は夏の半分以下ですが、油断は禁物です!積雪による紫外線の反射率は大きく、新雪では約90%が反射されます。雪面からの反射を合わせると、空から降ってくる紫外線の約2倍の量を浴びることになるのです。冬は紫外線量が少ないからといって、対策を忘れないで下さいね。
|
 |
|
|
|
オゾンは過度の紫外線が地表に降り注ぐのを防ぎ、私たち地球上の生命を守ってくれています。ところが、近年問題になっているように、工業製品やスプレーなどに使用されているフロンガスはオゾンを破壊し、生命や気候に悪影響を与えています。南極では、オゾン層の破壊が進んで穴が空く、「オゾンホール」と呼ばれる現象が観測されています。オゾンホールからは、多量の紫外線が地上に降り注いでしまいます。
気象庁による2000年のオゾン層観測報告によれば、南極のみならず、日本でも札幌・つくば・鹿児島の3地点でオゾン全量の長期的な減少が確認されており、オゾン減少の影響が出始めていることが分かっています。オゾン層破壊の問題は、私達のすぐそばに迫ってきているのです。 |
|