2T81シングル
20040504〜
目次
JRC・2T81
実験 20060702〜
以下、まだ妄想 20081002〜
増税前、駆け込み購入っぽいが 201403**〜
DC点火“再”実験 20150701〜
ダンパー管実験 20150704〜
DC点火“再々”実験他 20170208〜
DC点火“再々々”実験他 20170324〜
SEL菅野電機研究所の廃業!?・・・ 20170728時点
本番機の製作 まだです・・・
はじめに
私的メモランダムに「春先にタマ遊びの芽がうずく・・・」云々と書きまして、2004年はモロそのとおりになりました。表題以外にも「妙な」タマを入手しましたが、それぞれの頁で述べたいと存じます。
JRC・2T81
若松通商でもタマを扱っている事は承知しておりましたが、こんなモンまで・・・ずっと見逃していたのでしょう。早速2本買って実験、想像通りなので後年2本追加入手。その後・・・まあ今でも販売されてますが値段は倍増?!!!!・・・。
同社のHP写真だけでは「多分」程度の確証でしたが、811A系の国産球でした。
1990年代の首都圏在住時にも、国産811A系のタマを「某店頭」で拝見した記憶があります。ただ・・・2T81ではなかった気もします。
いずれにせよ「珍品」好きの態がばれてしまいますな。なお、入手した2T81はまさに米国系の構造です。いや、米811Aを持ってるわけじゃないのですが、RCA・812Aとそっくり。グリッドピッチは異なりますがね。
その812Aは、別構想で予備実験済み。本件と絡めるかどうか悩ましいのですが、最終形態未定のまま、2T81の点検エージングを兼ねた実験に取り掛かります。
実験
20040506〜
最終的にはEb≒700V、Ec≒+15V、Ib≒60mAまで試し、耐え、2本の差も少ない事まで確かめました。
2006年2本追加。先の2本の連番?「9050」「9061」に、今回の「9051」「9062」が加わり、なぜか気分がよろしい。印字向きが全て一致して、
更に気分がよろしい。
点検エージングの回路。これを眺めていて、「入出力を整えば音が出るかも」と想像しました。
思いつきを描いて(実験もして)みたのがコレ。ポジティブグリッド管ドライブの定番手法は悉く無視。
石政勉氏・中川洋氏の作例は承知の上。安易なCR結合が可能かどうかのお試しなのです。
今思えば、ブースターアンプで振りゃあ良かったと悔やみます。ドライブ電圧波形・歪みも観測して。
なお、実験で一番苦労したのは勿論「フィラメント・ハム」です。実体を知りたくて試みたAC点火では・・・最小30mV台とはさすがに酷い。
50Ωのハムバランサは①ピン側に寄ってます・・・ ・・・あれ?・・・。
同系管が無いので、812A(RCA)を試しました。三定数が違うので、バイアス抵抗を加減し、同じEb/Ib=450V/80mAにしますと、ハムは30mV台変わらず。ただしハムバランサは「ほぼ」中央に・・・ ・・・あれ?・・・。
あれれ?・・・
しばし、思考停止。疑問は先送りにして、DC点火を試します。
A電源は6〜12V/7Aトランスです。12Vタップをブリッジ整流し、「→R→22000μF→R→22000μF→」の豪勢なフィルタ(R値は記録忘れ)を奢って、ようやく0.75mVに。フィラメント①②ピン間のリプルは30mVrms (100mVpp)ほど。Rの発熱はすさまじく、コレ用に放熱器を与えている。フィラメント電力以上を食わせてるんだから。
その後、A・B電源トランスの位置を実験機から離すと、ハムが低下することを発見。PT→OPTへの誘導だったようです。これで0.6mV前後に。
最後には22000μFを夫々倍増、全88000μFでも、リプルは10mV台。ハムは0.4mV台に。
・・・こりゃ大変だ。
ヤケクソのTR式リプルフィルタ(後に簡易定電圧に)で、リプルは1mV以下に。でもハムは0.4mV前後か。もう疲れた。
すでに解体したのですが、2SC2238+2SC3519Aの2段ダーリントン。妄想中の最終形態に搭載するには熱過ぎ。
数値記録が曖昧なメモランダムから・・・AC8〜12Vからの整流をイロイロ試していた記憶。大雑把には、15〜25W程の熱損失を伴ったDC点火実験だったのだと。そりゃ熱くて当然だワ。
3行空けのために・・・こげなことを
6SN7パラドライブCR結合でコレ。前段込みのノイズが1mVほどなので、低レベルはこんなモン。前段の負担は重く、単体利得24db→14dbに。
注:2T81実験②.GIFの特性ではなく、RL=5kΩで測定・・・いんちきだなあ。
バイアスは+7.25V、Ic≒3mAです。前段利得は18.3dbと若干負担が少ない程度。動作基点から想像すると0.7WくらいでEc=0Vを跨ぐ?ドライブ状態かと思う。
余談ですが、実験初期に6SN7の発振を経験。居間の家人から「TVの映りがヘンだ」との訴えあり。実験室のTVでもそれを確認し・・・
だらしないバラック配線を整理し収まった記憶です。@5mA流した6SN7のパラですが手ェ抜きゃ発振すると、思い知った次第です、ハイ。
以下、まだ妄想
20081002〜
我ながら荒っぽい実験だったと自覚しております。しかし、殆ど10%台の歪みかと想像したドライブ実験が、案外「マトモ」なのは驚きでした。とはいえこの方針で進む気はなく、「真っ当」なカソードフォロワー直結が望ましいと考えます。いや・・・イントラ××がマットウじゃ無いとは言いませんが。
“ダイナミックカップル”はドライブ管のカソード負荷が「無い」ものを指すのでしょうか。加えてドライブ管のG1は接地電位・・・適合管が限られるのは詮無き事かと。「真っ当」かどうかは解りませんが、カソード抵抗と負電源で引っ張るのがよろしいかと存じます。ただ負電源が面倒臭いのも事実なので、ラ技「那須氏」の様なCH負荷カソホロドライブにして見ます。TC-30-50が入手出来ましたので。
実験で得た教訓としては、DC点火方法の改善ですね。TRリプルフィルタは効果を認めるものの、仕事柄信頼性に不安を感じてます。いささか保守的な考え方なのでしょうが、壊れた時は必ず「切れる」部品で構成したいなあと考えます。かといって6.3V4Aと同等以上の発熱もごめん蒙りたい・・・、そこでmH単位ででもイイのでインダクタンス濾波を思いつきました。
SEL菅野電機製作所のチョークコイル・SC-205を見つけたのです。磁気シールドが無さそうで誘導が怖いのですが、20mH/5Aともってこいのスペックです。また、管球機器用電源トランスを“まだ標準品販売”してたとは・・・本件にマッチしそうなPTも見つけました。
整流ロスの少ない「ショットキー・バリア」ダイオードを考える・・・ちゅうか、早くも日本インターのFCH20A15/FRH20A15を入手しました。実験しなきゃ。
正直申し上げますとこのModelはどんな出力管・出力段を念頭に置かれて設計されてるのやら・・・。380V巻線では450V内外のB電圧だが、120mAdcまでだから30W超級PPには足りぬ。5Vタップ付の巻線を整流管に使っても、6.3V6A巻線は・・・前段球で2A消費(なんだそりゃ)して、出力管向けに4Aは有り余る。
バイアス用Sub巻線・タップもない・・・
つい・・・妄想してしまいました。平田電機タンゴと菅野電機SELのコンビです。問題は、TC-30-50に見た目が似合うFW-20Sの目処がつかない・・・。
前段管は安易に6BM81本で済まそうと考えました。カソホロでの減衰が読めませんが、まあ頃合の利得があり、若干の負帰還も期待。6RK19は電圧遅延用で、H巻線は前段と共通。H-K耐圧に“賭けた”机上空論?。
負帰還ループにCHを内包するので、6db内外の低帰還でも帯域端の按配は結構シビアかも知れません。なあに、ムズカしい様なら止める。
本機はやや“緩い”設計方針で、楽したい・・・と考えました。SELのトランスで、多少は楽できると思ったのです。懲り倒す向きは「812Aシングル」で試す所存ですので。
ちょいと補足を
「ダイナミックカップル」なる呼称・・・、これは浅野御大がお書きになった文献が大元かと思い込んでましたが、6AC5-GT(RCA)のデータシートに「DYNAMIC-COUPLED CONNECTION」と書かれた、例の回路が載ってました。ソコではドライバ管のカソード⇔GND間に25kΩが挿入されています。+13Vのバイアス電圧からすりゃ0.5mAほどの分流なのですが、「英文注釈」のYhoo翻訳では、起動時の過大電流防止のためにある・・・と読みました。前後の球の起動タイミング(多分個体差も?)が絡んでそうです。
ところで皆さん・・・無くて大丈夫でしたか?。
もうひとつ。故藤井秀夫氏の示唆かと記憶しますが、ドライバ管のIb=出力管のIgでは、フルスイング時のカットオフ、または近似の状態で両者とも直線領域から外れています。出力段の都合は手の加えようがありませんけど、ドライバ管はカットオフを避ける手があると・・・。負に引っ張るンだそうです。フツーの負バイアス出力管をカソホロ直結するのと同じですな。そしてCH負荷は、負電源要らズでも同様の効能が得られると考えています。
20180627:追記
「6AC5-GTシングル実験」はぢめました。順番が逆だぞ、とのご指摘には「ハイ・・・今頃気付きました」と、取って付けた言い訳をしましょう。
増税前、駆け込み購入っぽいが
201403**〜
実は、ステレオ2ch分ではなく、片ch分のSELトランスを購入。一番の懸念材料であるDC点火が成り立つかどうか、磁気シールドにも不安があるので、手持ちのU-808でお試し実験したくなる。上手くイカン様なら・・・考えます。これが2ch分買ってペケですと、精神的ダメージは大きいでしょうなあ。
10Hチョークはシャーシ上面配置に“耐える”容貌。20mHは・・・隠したい。深いのが要るなあ。
5行空けのために・・・こげなことを
増税後2014年6月、TC-30-50に“合わせる為”だけの理由で入手した、旧TANGO・FW-20S。
運良く新品の在庫店を知ったのですが、店主の「他でもイイのがあるでしょうに・・・」とでも言いたげな顔が目に浮かぶやり取りでした。でも、並べてみると他機では得られない“シックリ感”は格別ですなあ。
之奴の入手で安心しちゃって、予備実験が先送りになった気がします。
3行空けのために・・・こげなことを
DC点火“再”実験
20150701〜
現在着手中の2B33シングルで、“着せ替えゴッコ”を楽しみたかった某著名球?が酷いHハムを出します。それのDC点火実験のついでに、本件懸案の一つ、SELのトランス群で目論見が果たせるかを・・・今頃検証してみたのです。10年ナニやってたのやら・・・。
2T81の代わりに6.3V4A定格相当の1.575Ω負荷を拵えました。DMM測定では1.66Ωなどと示しますが、菊水PMC18-5Aからの給電テストでは4A表示時に6.31〜6.32V・・・電流がデカイと安易な配線材・半田付け部などがバカになりませぬ。
日本インターのFCH20A15/FRH20A15は・・・ど〜も華奢に見えて・・・、過日見つけた新電元のSDBブリッジ「D30XBN20」を新調しました。30A200V品だそうで、頼もしく感じたのですが・・・さて。
22000μFではリプル電圧に不満。所要ACライン電圧も微妙・・・。
6.3V6A巻線からのAC電流値を見ますと・・・これも微妙に超過。DMM・PC-510のAC10Aレンジ挿入ですが、コレの抵抗分?で緩和されてそうな値かも。
AC実効値指示のクランプメーターの新調を考え(まだ悩んでる)ましたが。
結論言えば・・・失敗です。新調SBDブリッジでも、SC-205チョークでの電圧降下分を回収出来ません。
コレには凹みました。PTは6.3V6A巻線だけの負荷状態なので、他巻線にも予定の負荷が加われば更に下がると予想されます。整流直後の平滑容量を倍増しても6V超が得られる見込みは無いと考えます。
なお、リプル除去効果だけは抜群で、DS...での波形観測では痕跡すら見えません。う〜ん・・・死蔵するのは惜しいので、他機用途への転用を考えます。
22000μFは2004年のハム実験に用いたモノ。漏れ電流だけは20μA(10V印加)以下を確認。しかしDMM・PC-510のCレンジでは容量が過大で読めません。LCRメーターほしいッ。
些細な事かも知れませんが、4Aの整流時で平滑コンデンサに流れる「120Hzのリプル電流値」は如何程でしょうか。この手の解説は滅多に見られず、武末数馬先生の文献で知る「直流負荷電流値の1.4〜1.6倍」の簡易式だけです。おお、本件では5.6〜6.4Armsにも及びます。
さて、実験に使い、ホンバンにも使いたい松下電子部品(1990年代購入と思うので)のケミコン「TSU CE」モデルは耐えるでしょうか。今ではデータシートなど見つかりませんので、他社の同定格モデルを2〜3調べてみました。概ね4Arms台(定格上限温度時)が示されていました。
7/1の実験では、ケミコンのリプル定格を超えていたようです。まあ、数分〜10数分?のテスト中に気付くほどの発熱は感じられませんでしたが、注意を要するところです。ちなみに、811Aシングルの作例で、10000μFクラスのを拝見しますが・・・耐えてますか?。
断念したSEL・SC-205使用評価実験の直後。接続を外したトコロで慌てて撮影。
3行空けのために・・・こげなことを
SC-205・CHを諦めて、若干の抵抗挿入を試みた実験です。
2行空けのために・・・こげなことを
計算する知恵が無いので、数値変更実験で最適値を探す体たらく。
←6.3V6A巻線端子電圧波形と、挿入抵抗両端の電圧波形を観測しました。
巻線電圧波形は、イマドキの電灯線電圧波形を反映してます。
抵抗両端電圧波形は・・・実は初めて見るのでしんぢるしかないのです。RMS演算値を0.055Ω(J級0.22Ωを鵜呑みに)で割りますと・・・約6.3Armsですって、信じますか?。
抵抗両端波形のVmaxとVmin演算値を0.055Ωで除算しますと、正負のピーク電流値が約±11.5Aと概算できますが・・・う〜む、でかい。今頃ですが、整流器の順方向電圧ロスは、このピーク電流値で判断するのが正解かと気付きました。
2行空けのために・・・こげなことを
←抵抗両端波形はともかく、RMS演算値は前述の波形時に似てます。つまり・・・同じく約6.3Arms流れてるって事かと。で、この交流電流?は平滑コンデンサにも流れてると考えますが、さて。
下の実験二題はDMM・PC-510のAC10Aレンジを“無理矢理”挿入したモノ。電圧降下がバカにならず、PT1次側電圧は100Vを越えてます。まあ・・・ナニやってんだか自分でもよォわからんくなっていた実験ですが。
挿入抵抗値が微小だからか、理屈でもおんなじ?なのか解ってませんが、DMMの指示値は変わりません。誤差含み満載の実験だろう事は承知しておりますが、DMM挿入分でもピーク電流の抑制→RMS値の減少が見えた・・・と解釈したい。
最下段はオマケ。6.3V6A巻線の直流抵抗値を調べてみました。概ね0.03Ω台と思えば、0.055Ωの外部挿入抵抗値が無意味とは思いたくないのです。コジツケですが。
3行空けのために・・・こげなことを
プローブが噛んでるのは、整流器前に挿入した0.22Ω2W×4パラ抵抗。総合2W強の損失で、触ってもそんな感じ。シャーシ内蔵は可能な範囲。
SEL・SD-3812を使う限り、これ以上のリプル(100mVrms)低減は無理だと思います。最終的なリプルハムはそれなりの・・・まあ、無帰還時1mV未満が得られる程度かと想像します。
近年の作品の中では、イマイチだ。
6.3V6A巻き線からの負荷電流は6A超が確定の実験です。それに・・・ピーク電流値も半端でない・・・見なきゃヨカッタ気がして。
ダンパー管実験
20150704〜
「以下、まだ妄想」で述べましたが、B電圧の遅延用に6R-K19を用います。データシートから、DC100mA時のP-K間電圧は10Vほどと知りますが、“入手した”タマの実態を実験で確かめました。心配性が過ぎますか?。
いささか無駄の多い実験回路でしたが、ヒーターの接地間に電流計を挿入すれば漏れ電流が直読できたなあ・・・と悔やむ。
写真は東芝サンプル①。サンプル②③いずれも10V未満で良好でした。
NECのサンプル①②では11V台で・・・まあ、可の範囲かと。
6R-K19はH電力だけで7.56Wも食い、P入力が1Wほどでも熱いぞ。
前年から揃えつつある菊水直流安定化電源PMCシリーズのおかげで、プチ実験が楽になりました。が、このまま一気に製作へ・・・・とまでの決断には至ってません。着手中のアレが待ってました。
DC点火“再々”実験他
20170208〜
往生際の悪い第三弾。昨年1月、更に低VfだろうSDBを見つけました。新電元「D20XBS6」は60V20Aですから、定格・規模は縮小に・・・。でもVf≒0.6V(10A/25℃)は、同社「D30XBN20」の0.8V(同条件)を下回ります。2素子直列分≒0.4Vの差ですが、期待。なお、整流器を流れるピーク電流値は、“10A超”だと体感して(計算して導き出せるのかは・・はて?)おります。整流電圧を推し量るなら、負荷電流の4AdcでVfを調べるのではいささか・・・語尾ボカシました。
入手から○○1年・・・今頃試すッちゅうスロー・ライフやってます。
結果は・・・びみょ〜に不足です。ほんのチョッピリでいいから入れたい「ピーク電流抑制抵抗」は無理ですな。それにPTの全負荷やったら、更にVfは下がる予感・・・困った。
前使った「6.3V4A定格相当の1.575Ω負荷」は・・・解体されまして。で、ご本尊の2T81そのものを負荷にしてます。ただし、電流経路にナニか挿入したらそれだけで電圧が落ちちゃう気がして、実際のIfは未調査です。
陽極への100V印加は「Ib=0」では陰極がボケる?との言い伝えを信じてのお呪い。最初に試した10mA程度では効き目が心配なので、Vf減のIb値に与える影響も見ようと50mAに増量したのですが。
些細な事かも知れませんが、Vf>5VdcでIbの微増加が見えました。50→50.5?くらいの電流計指針の動きは、ナニか変なことしたンか?。
↑の実験に、OPTとドライブ段を加えりゃ実機の掴みが出来そうだと思いました。ただし、目論みのB電源回路をバラックで組み上げるのは怖いし、いささかメンドウです。PMC350...の給電から試しましょう。そして、ドライブ段は安易にもMOS素子で。
まだ出力管ナシなので、22mA程度のIdo動作です。CH両端の22kΩは不用なのかも知れませんが、インダクタ負荷の回路で不用意なON/OFFやると・・・怖い事が起きそうなので。
MAK-6630の+14db(10Vrms)出力のまま、安易なF特とTHD特性を調べました。なお、DS-5102Bで観測したソース波形の演算数値の中に「Vmax=26V、Vmin=−2.8V」が読めて、CH負荷ならではの負領域スイングが見えました。抵抗負荷ではマイナス電源で“引っ張ら”ないと出ない部分です。
10Vrmsでは2T81を振り切れませんが、445冶具の20Vrms超を入力すれば・・・+40Vほどまで出るかと妄想してます。100V未満の電源電圧でも充分だろう点は半導体ならではかと。
さて、妙なF特ではないだろう事は確認。しかし・・・200Hz以上での歪み増加は意外でした。
気に食わんが、2T81シングル出力段には事足りますのでガマンします。
最終的には6BM8でやりますから、その時には更に詳細な測定をしましょう。妙なイロケを出さぬ範囲で。
今頃負荷線計算してます。最終的妄想動作ではなくて、350V供給の掴み実験条件です。
特性曲線のEb-Ib範囲が広すぎて読み取りしづらいのですが、3.5kΩ負荷線上で+40Vチョイ振ればibmax≒150mAかと。Pomax≒10Wを期待します。なお、バイアスは+20Vチョイかと思うので、TC-30-50に幾らかの固定抵抗を足す事になろうかと。
大雑把すぎるので、グラフへの数値挿入を省略。5Vやら5mAレベルの差が読めませぬ。
****
2T81の掴み実験で、フィラメント点火を含め全てPMC...シリーズからの供給です。写ってませんが左に445冶具あり。
Vf<6.3Vの減電圧で、クリップレベルが変わるか変らンかの見極めが主眼です。著しく影響が現われるなら・・・再放置ネタを覚悟。
まずは基本性能から。G1入力1Vrms・1kHz→8Ω負荷出力まで、A≒0.717(≒−2.9db)でした。案外良い電力感度は高μ管だから?。2SK310ドライバ前の短絡で、Noisは0.1mVrms未満(500kHz・BW)なのですが・・・バラック配線への外来Noisが無視出来ぬ印象でした。
TC-30-50に固定抵抗を足したのは、バイアス電圧が高い為です。巻線抵抗485Ω(公称値)だけで進めたら・・・50mAの定格を超えそう・・・と、実験途中で気付いたっちゅうポカしました。2SK310への損失負担もあるしね。
期待の10Wを達成したかに見えるカーブでも、実質8Wで頭打ち開始。
先にクリップして、その時まだカットオフ側の湾曲は緩やかです。Ibo=80mAはFW-20Sの規格で決めただけですから、ADJの余地有りかと。
右は1kHz歪みカーブを引用し、その出力時のグリッド電流をプロットしてみました。クリップ手前からの増加は・・・こんなモン?。
G1ドライブ波形歪みも見ましたが、MOS+CHだけの実験で見た高域歪みも現われてます。ただし出力段に対しては十分な数値かと。2T81への打ち消し無し“生歪み”ですが、本件初期に試みた「乱暴な回路」から半減。目論みの6BM8ドライブでこのレベルを再現できりゃ嬉しい。
CH歪みの分離・抽出などしてない測定ですが、Gi入力歪みの底値(0.01%前後)辺りでは、「CH実験」で体験したようなTHD数値の揺らぎを見ました。依然としてナゾのままです。なお、8Ω負荷低出力時の100Hz歪みが、0.3%で底打ち。これは高rp管故のOPT歪みでしょう。100Hz以下の周波数では・・・調べる(知る)のが怖い。0.02W上の出力時も1k・10kHzのカーブから若干乖離しているのは解せません。
F特の詳細やら出力Zは「後の楽しみに取っとく」ことにしました。高rp管ならではのチープな数値性能が見えるかもしれない・・・と、ワクワクしてますが偏ってる?。
なお、Vf減の影響はありました。
Vf=6.3→6.0→5.5Vに対して、無信号時Ibo=80→79→76mAに。
Vf=同上に対して、無信号時Ig=12→11.7→11.3mAに。
Vf=同上に対して、Pomax=10.1→9.9→9.2Wに。
Vf=同上に対して、THD(1kHz)=5.6→5.42→5.18%に。
Vf=同上に対して、Ibmax=83→82→79mAに。
Vf=同上に対して、Igmax=16.1→15.1→14.1mAに。
注:Pomax=10.1W云々は「9Vrms/8Ω設定」にすぎず、波形上の特定状態を決めたものではありません。クリップとカットオフ側の湾曲がいささか進んだ波形ではありますが。
初めてのテスト項目ですし、「9051」サンプル1個だけなのでなんとも・・・。ただし、数値変化が“見えた”事には驚きました。ただし、それぞれの波頭付近を注視して見つめましても、変化が読めないのです。波形全体に微細な減少が及んでいるかの印象。歪み波形そのものも変化が見えないまま数値は同じく微減・・・。ズバリ「増幅度の減少」が読めたのだと言い切りたい。
ありていに言えば6.0V点火では実力を発揮しきれないのだ・・・とも思えるし、こんな程度なら放ッとけ・・・てな考えも湧く。困ったモンで。
RCA標準動作例のB級PP並みのibmax>500mA(CCSの178W例だが)と思われる領域などでは、異なる変化が見えそうな気はします。
以前のMJで、大塚久氏がされてたようなエミッションテスト方法を承知しています。タマ単品の能力差評価としては一目瞭然なのでしょうが、アンプ動作への影響にまで踏み込まれてなかった記憶。などとエラそうに書いてるジブンは試した事無いので・・・大きな口叩くのは僭越でした。m(_ _;)m・・・
やや深入りの実験ついでに、4本のVf減電圧動作を調べました。
多分、Gmの減少が表れたんだな〜くらいの解釈してます。なお、「A<0.7倍」なのは既に波頭が抑圧された出力で調べちゃったので、1Vrms入力時とは異なります。
まあ・・・良く揃ってる・・・って事くらいしか解りませんな。811系はコレしか持ってないので、812系と比較したら変かなあ。でも実験装置では負バイアス出来ませんからやれないのです。
3行空けのために・・・こげなことを
DC点火“再々々”実験他
201703**〜
前回の実験にて、6.0V点火の中途半端さを“知ってしまった”ので、ど〜にも○○○の納まりが悪いのです。
 Vf=6.3Vdc確保のため、SEL菅野電機に「SC-205・チョークの巻線抵抗“半減”仕様品」を特注してしまいました。引き換えとなるインダクタンスは、半減程度なら御の字です。
Vf=6.3Vdc確保のため、SEL菅野電機に「SC-205・チョークの巻線抵抗“半減”仕様品」を特注してしまいました。引き換えとなるインダクタンスは、半減程度なら御の字です。
10mH・5A定格ですが、DCR=0.121Ω(添付の仕様書から)にキッチリ拵えていただきました。有難うございます。
お値段はン倍増に。御見積りしていただいた担当の方も「2個ですから・・・」と言い辛そう。
ヨソ様に特注するっちゅう選択肢もありますが、既に一個入手済みのC-1020と取り付け穴位置が一致してるのが条件です。後に述べる意匠に絡みますが、むやみに異なる外寸比もイヤなのです。SC-205形状寸法の同等条件まで付けたら、受けてくれる他社ある?・・・てな。
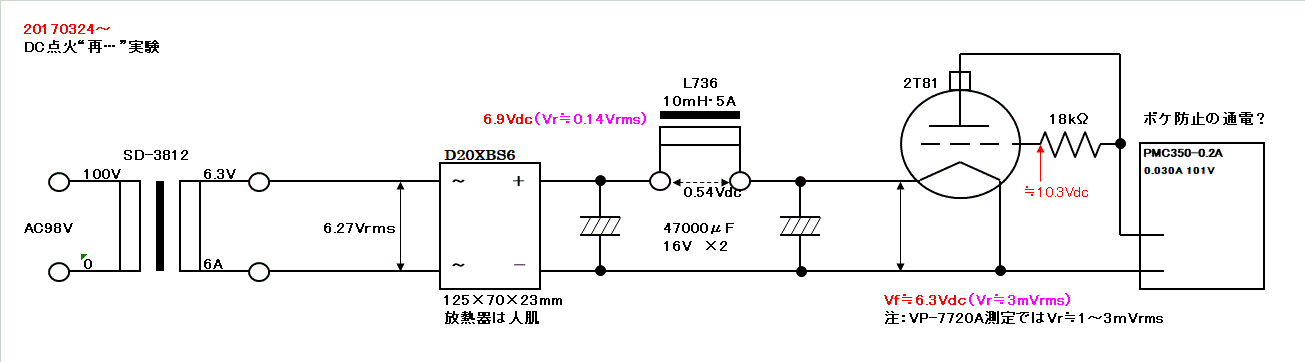 ナントカ6.3Vdc+αを達成できて安堵しました。整流器前にピーク電流抑圧目的で微小でも抵抗を挿入する余地があるかも。
ナントカ6.3Vdc+αを達成できて安堵しました。整流器前にピーク電流抑圧目的で微小でも抵抗を挿入する余地があるかも。
インダクタンスは減ったけどリプル電圧が減ったのは、47000μF×2の賜物かと。
一部を除き、測定数値はDMM・PC-510/同510aです。
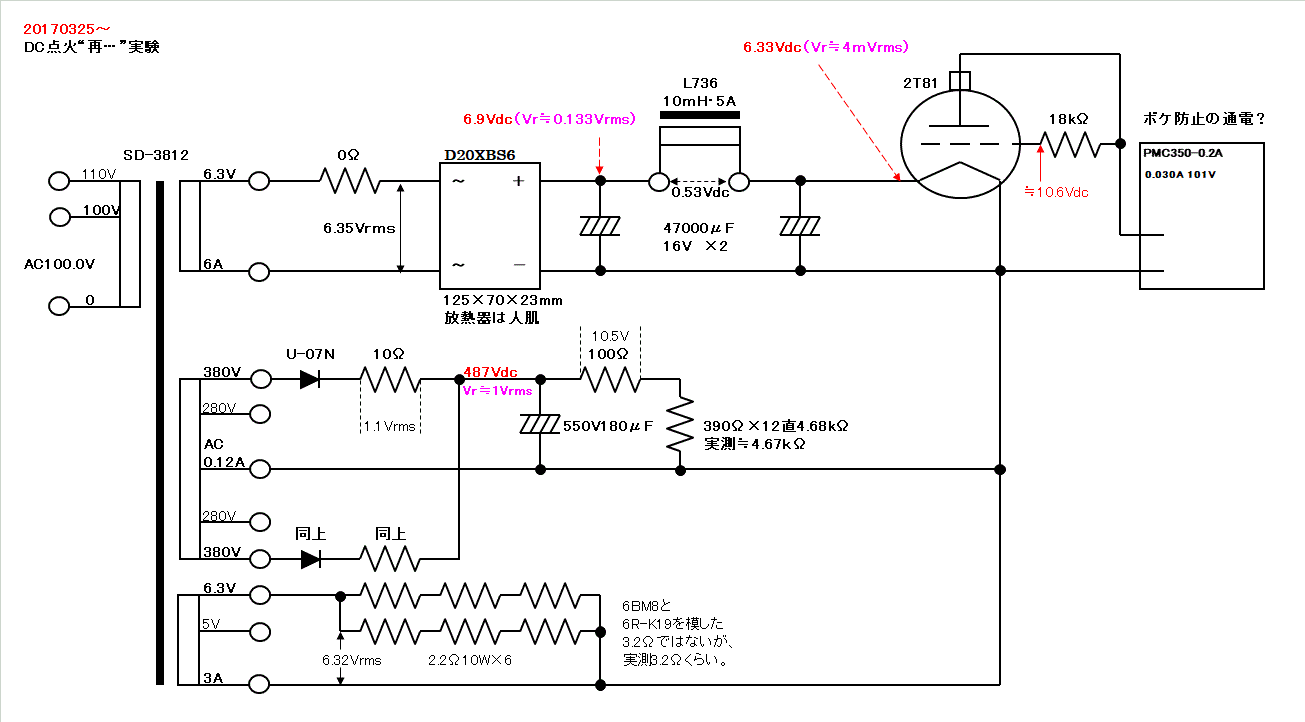 380V×2巻線と、6.3V3A巻線に想定負荷を付加した実験です。
380V×2巻線と、6.3V3A巻線に想定負荷を付加した実験です。
全負荷ではないが、全巻線使うと+α分は帳消しに。今更の話になるけどCHのDCR<0.1Ωを指定すりゃヨカッタちゅう落ち。ワタクシの判断ミスで御座います。
この際だからと、380V巻線の整流平滑回路も簡易テストしまし、概ね100mAの負荷電流に490V近く出ました。ただしカソホロドライブ段は280V巻線から給電する予定ですから、正確な負荷状態を模しておりません。
電圧起動の遅延目的で挿入する6R-K19、C-1020・CH、OPT・FW-20Sの1次で落ちる分を差し引いた、2T81の正味Epの見込み450Vは大丈夫そう。
測定数値は・・・同上でございます。
毎度だらしない配線の実験ですが“本番”で少しは整理しますから。
SEL・SD-3812の奥に、旧タンゴ・FW-20Sを置いてみました。2T81の内部抵抗値がわかりませんが、RCAの特性曲線から20〜30kΩと想像し、FW...の1次を27kΩで終端。2次は⑤-⑥間に8Ω終端・・・1次5kΩ使いを想定して8Ω負荷のハムNoisを調べます。
磁気シールド構造が見当たらないSD-3812と、rpが高い出力管を模した誘導ハムテストですが・・・相当隔離しないと結構なのが出てくる結果。ここでは隠蔽します。ちなみに1次1kΩ終端では、2次8Ωに1.4mVrmsでした。
DS-5102Bでの波形観察、波形SAVEもしましたが、これも今ンところ隠蔽します。PTの隣り合わせ(磁束軸方向も)など極端な最悪条件例です。なお若干の別配置確認しまして、1次終端27kΩ時でも1mVrmsを切ります。ただし近年の完了品で達成している無帰還0.1mVrms内外は困難かも知れず、ここまでのDC点火の苦労は水の泡になる予感。
どうやら直熱管の第一作目になりそうな勢いで進んでいます。仕掛品止まりの「2A3Wシングル」を“片付ける”のが先だ・・・と思いつつ、なぜ後回しになるのか自らをを問いながら。
手持ちの6BM8には、「16A8超3結」でも試したン本と、それだけぢゃ心許ない気がしたので、ン年前に新調→死蔵の露EHブランドが御座います。
でもまだ心許ないな〜・・・と探しまして、新たな中古?東芝×2と松下×2、そして蘇維埃時代の相当管・・・と称して売ってた6F3Pを4本を追加しました。これだけありゃ十分だろ?。
「超UL実験」の基盤残骸を再利用改造して、6BM8の前段回路実験を試みました。所要の利得・最大出力電圧などと共に、AC点火時のハム調査を重視して調べました。
AC点火時の画像ですが、菊水PMC18-5AによるDC点火も試しました。なお6BM8(T)は同PMC350-0.2Aからの350V供給、同(P)三結カソホロはPMC250-0.25Aからの200Vで。
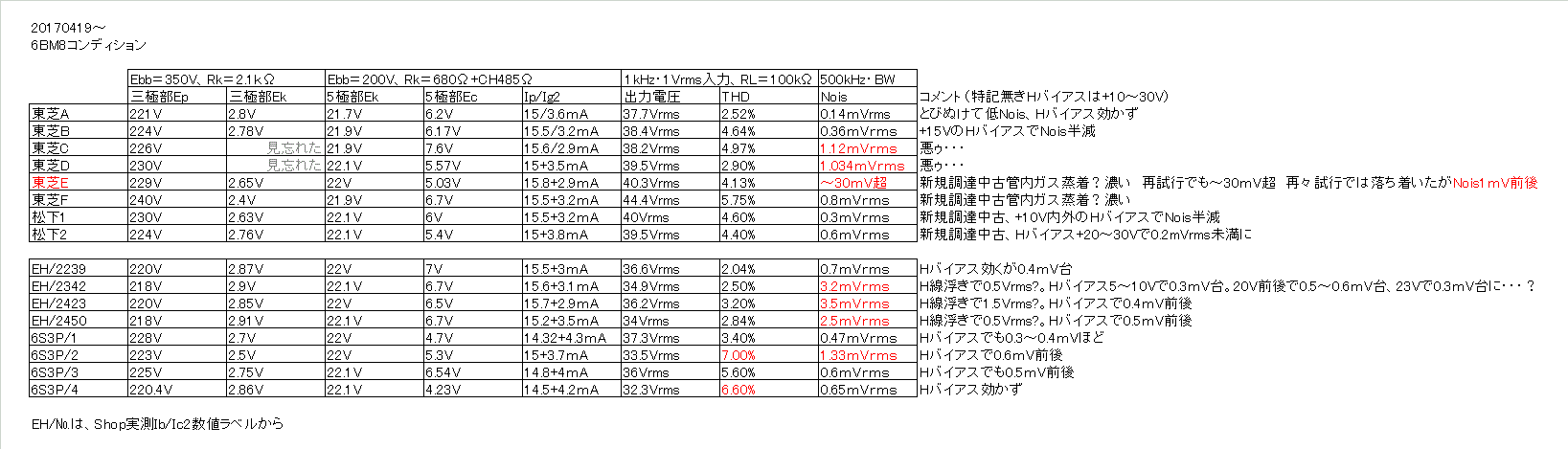 大雑把な結果です。露・蘇維埃球はIh>0.8Aだげな・・・と今頃知る。
大雑把な結果です。露・蘇維埃球はIh>0.8Aだげな・・・と今頃知る。
国産球は全て中古。かの国のは全部新品と信じるが・・・これまたハムはばらつきます。PMC160...で、〜30VまでのHバイアスも「効く個体がある」程度の結果。効く電圧範囲が見つかったりして興味深い。EH球の3本は酷い結果だがHバイアスで実用になる。そもそもH線を浮かすとハム減る(3/4本が)って・・・ど〜なってんのやら。
EH球のンmVrmsハムもPMC18...でDC点火すりゃ当然のごとく静か。東芝1mV超球も同様。
他の静特性は、似たようなものかと。精密に動作条件を固定していないので、「並み外れ球」発見の目安程度です。NGを断言できる個体は無く幸運?、でも怪しいのがある。
あとで改めて詳細を述べますが、三極部入力からカソホロ出力までの増幅度は、アナライザZin≒100kΩ時に32〜44倍(G≒30〜33db)でした。初段Rk=2.1kΩ固定の実験だから個体差もそれなりに出ますが、おおむね60Vrms以上でも数%の歪み。出力管の入力インピーダンスが分からんのですが、DC的解釈?ではZin=22V/12mA≒1.8kΩで、6BM8Pにとっては相当に重い負荷ですな。インチキっぽいが、2.2kΩをカソード⇔GND間に負荷しますと、カソード電圧は21Vチョイほどの低下に留まり、同時に出力管へのIgを模した約10mA分、6BM8P三結のIbも増加します。A≒33(+30db)ほどに減り、40Vrms以上での歪みは悪化しましたが、なぜか以下のレベルでは半減近い低歪みに。ただし歪み波形はやや汚くなりました。三極部の歪みとカソホロの三結五極部との歪み方を切り分けて調べてませんから、何がその歪み方の差を生むかは理解しておりません。
欧米のECL82/6BM8は持っておりませんし、高いから買えません。でも試してみたくもなった実験でした。ところで中華の相当球ってあったンでしたッけ?。
SEL菅野電機研究所の廃業!?・・・
20170728時点・・・
気付くの遅ェよ・・・と、自身に問う痛恨の迂闊。増税前にST分買わンかったツケだ、との後悔先に立たズ事例ですな。以後、何を書いても愚痴っぽくなる気がする。なを、SEL特注CHのL736と合わせてシャーシ上下に搭載するつもりのC-1020は、在庫店(増税前購入したトコ)に即注文しGETしました。これだけでも、あ〜ヨカッタと&します。
・・・
・・・・
・・・・・(-公-;)ウーン
・・・(有)春日無線変圧器の「特注電源トランス」に頼ろうかなと。明朗会計なのはココしか存じ上げませんしねえ・・・。
SEL・SD-3812はギリギリ150AV未満ですから、O-BS500で同一定格のを巻いていただけるのですが・・・ちょっと待てよと。6.3V6A巻線では2T81点火ギリギリのフィラメント電圧がヤットコサでして、整流器前に挿入したいピーク電流緩和抵抗(と勝手に呼称)の余地がありません。200VAのO-BS700でも外寸占有面積が同じですから、プチ高価でも過不足の修正を盛り込みましょう。
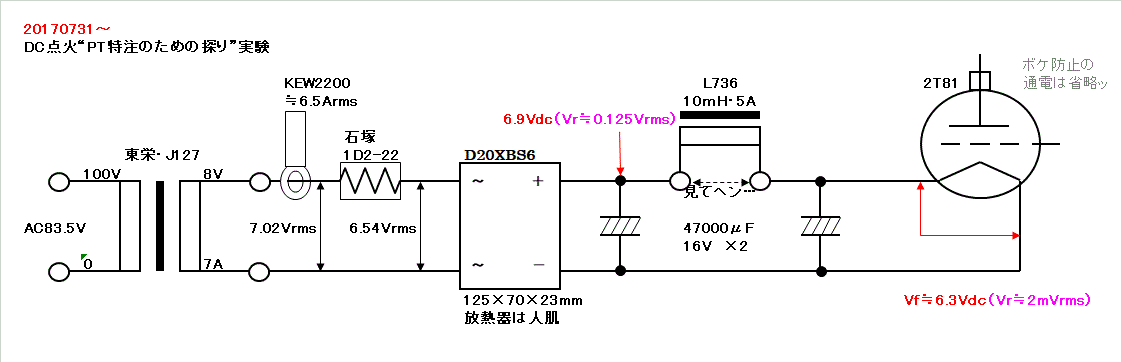 200VA品のO-BS700でも2次巻線の上限電流値7A(6A未満ぢゃなくてラッキー)は決まりです。諸実験に使いまわしてる東栄・J127汎用トランスで、過剰過ぎない範囲の電圧設定探り実験です。
200VA品のO-BS700でも2次巻線の上限電流値7A(6A未満ぢゃなくてラッキー)は決まりです。諸実験に使いまわしてる東栄・J127汎用トランスで、過剰過ぎない範囲の電圧設定探り実験です。
7V7A巻線で決まりですかな。ついでに往生際のナンタラ・・・何回目?。4Adcを得る各部AC電流値を調べるために、ACクランプメータKEW 2200Rを導入してしまいました。
ブリッジ前に挿入してみたかった、石塚NTCサーミスター・1D2-22は「どえりゃ〜」熱い。最大許容電流12Aと聞くが大丈夫か?くらいに。クランプメータ指示値の約6.5Aと両端電圧からの概算では0.09Ωを得るが、残留抵抗値0.04Ωには満たないので、まだ“熱さ”が足らンてか?。気にはなるので、然るべき放熱対策込みの固定抵抗に置き換える事も、考えときましょう。
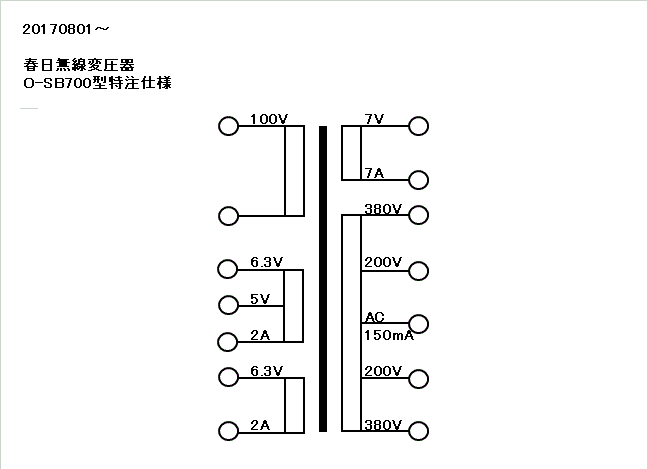 もう“廃業騒ぎ”の落胆はご免被りたい・・・いや、春日さんがど〜こ〜ではありませんが、すぐ左記仕様で注文しました。
もう“廃業騒ぎ”の落胆はご免被りたい・・・いや、春日さんがど〜こ〜ではありませんが、すぐ左記仕様で注文しました。
200VA容量に余裕がありますので、380V・B巻線も0.12A→0.15Aに強化。ついでに280Vタップ→200Vへの変更と、6NM8と6R-K19のH巻線も分離増強しました。全188.2VA、端子数14個は上限。
そして評判通りの速度感で届きました。特注番号「№H29-08042」PTはSEL・SD-3812よりコア厚みは増したが、幅・奥行きはプチ縮小寸法なので、妄想意匠への変更は避けられます。
・・・余ったSD-3812の処遇は・・・今ンとこ“売る”習慣が無い・・・。しかし一個だけでステレオアンプかあ・・・6.3V球前提で、Eb≒400〜450V・・・どんなタマが合うのやら。
大昔に買った一式のトランス以後も大した顧客ではありませんでしたが、老舗のメーカーがまた一社消えゆく寂しさは、何とも言えませぬ。L736特注は廃業(4/20と聞く)直前の依頼だったのだと思うと、ゾっとしませんな。